真言宗の戒名の値段相場と一覧|院号・位号の違い/6文字の数え方
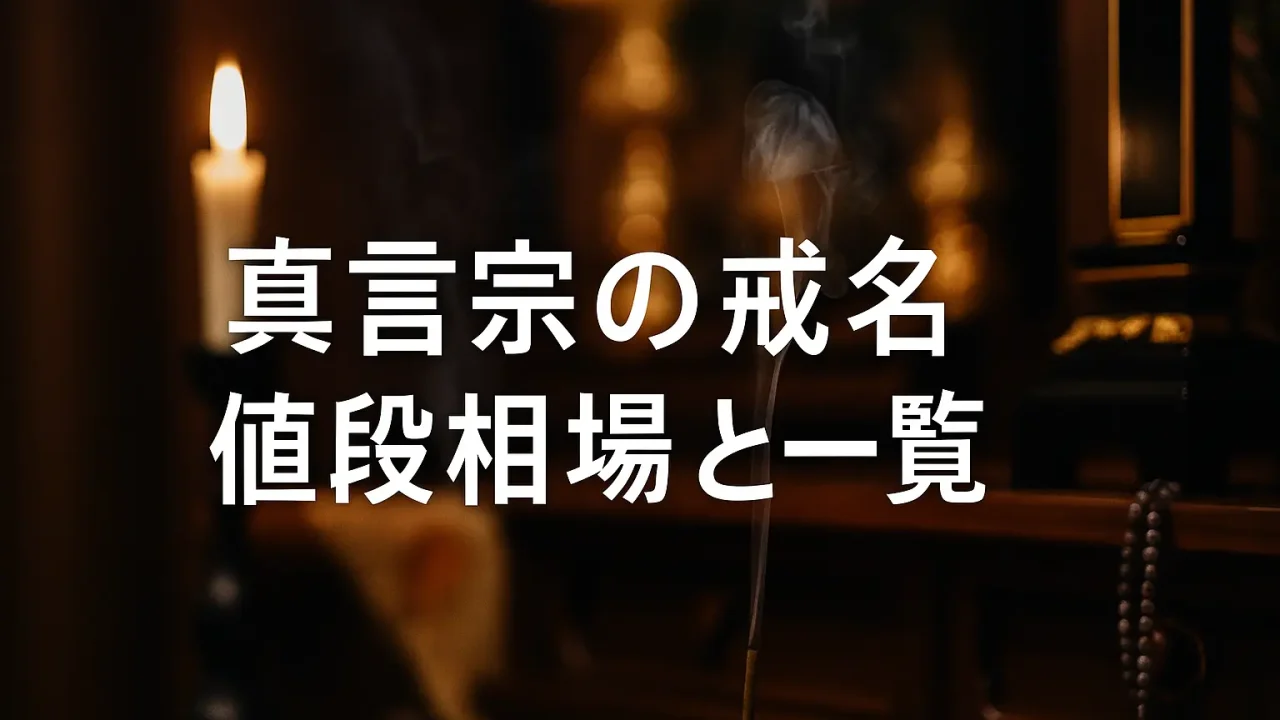
初めての葬儀で「真言宗の戒名はいくら?」「院号や位号の違いは?」「6文字の数え方は?」と迷っていませんか。
本記事は、戒名とはの基礎から値段の決まり方、相場一覧、ランク(院号あり/なし)別の目安、戒名の付け方までをやさしく解説します。平均額に振り回されず、内訳と条件で比較できる“納得の判断軸”をお持ち帰りください。
【結論】真言宗の戒名の値段相場と判断軸
真言宗の戒名の費用は、寺院の運用や地域慣習、そして院号(戒名の前に付く尊称)・位号(居士・大姉・信士・信女など)の選定、儀式の範囲によって数万円〜数十万円まで幅が出ます。
平均額だけを追うより、どの要素が値段に効くのかを整理し、家族の希望と予算配分を明確にしてから菩提寺へ相談しましょう。
結論としては、①院号の有無、②位号の選定、③地域・寺院・儀式規模の三点を押さえ、内訳(読経料・戒名料・お車代等)と条件を同じ土台で比較するのが失敗を防ぐ近道です。以下で各要素の見方を示します。
ランク(院号の有無)でどう変わるか
院号は「○○院」のように戒名の頭に付く尊称で、地域社会や寺院への貢献、信仰実践、家の先例などを総合して授与されます(必須ではありません)。一般に院号が付くと費用は上振れしやすく、「上位ランク」と理解されがちです。
重要なのは「格を上げる=必ずしも最善」ではない点です。供養は一度きりではなく、追善供養(年忌法要など)に回す予算とのバランスを取ると納得感が高まります。
例:小規模葬+院号なし+年忌を丁重には、限られた予算で満足度を高めやすい配分です。判断時は、院号の基準・可否・費用差の根拠を寺院から説明してもらい、メモとして残しましょう。
位号と値段の関係(居士・大姉・信士・信女)
位号は戒名末尾に添える称号で、一般に成人男性は居士/信士、成人女性は大姉/信女などを用います(地域差あり)。位号の違いが費用に与える影響は寺院ごとに幅があり、院号ほど明確な差が出ないことも珍しくありません。
選定では「格」だけでなく、故人らしさが伝わるか、既にある家族の戒名との整合(並び・字体)、読み上げやすさを重視します。
実務ポイントとして、①位号の基準(年齢・性別・地域慣習)の確認、②表記(旧字/新字体・読み)の統一、③変更可否と費用の扱い——の3点を面談で押さえておくと後日の手直しを防げます。
地域差・寺院方針・儀式規模による上下要因
同じ構成でも、都市部か地方か、菩提寺(檀家)の有無、通夜の有無や僧侶人数・読経回数などの儀式規模で総額は変動します。さらに遠方の場合はお車代・宿泊費が加わることも。金額を「平均」で捉えるより、内訳と条件を揃えて比較する方が実務的です。
- 内訳の確認:読経料・戒名料・お車代・御膳料・交通宿泊の扱い(総額か分離か)。
- 範囲の確認:通夜の有無、一日葬・火葬式か、僧侶人数、読経回数、会場(自宅・式場・寺)。
- 表記の確認:位牌・過去帳・墓碑での字体と並び、清書前の下書き(校正)の有無。
ケース比較:A)院号なし+信士(信女)+一日葬(僧侶1名・読経2回)は整った供養を保ちつつ費用を抑えやすい構成。B)院号あり+居士(大姉)+通夜・葬儀あり(複数名・読経増)は相応の上振れが想定されます。どちらも正解になり得るため、価値観と予算配分を言語化し、寺院と早めに共有しましょう。
真言宗の戒名とは|意味・役割と他宗派との違い
戒名は、仏門に帰依して戒を受けた者の「仏教徒としての名」です。真言宗では、通夜・葬儀から年忌法要まで一貫して用いられ、位牌・過去帳・墓碑など供養の記録にも刻まれます。
法律手続き(死亡届・火葬許可申請等)は俗名で可能ですが、仏式の供養を丁重に進めるうえでは戒名が実務上の基盤になります。ここでは、用語の基本、真言宗での位置づけ、実際に使われる場面を整理します。
「戒名とは」何か(用語と役割の基本)
一般的な構成は、院号(尊称・任意)+道号(志や人柄を示す語)+戒名本体(通常は二字)+位号(居士・大姉・信士・信女など)。すべて必須ではなく、寺院の方針や地域慣習、家の先例を踏まえて組み合わせが決まります。
- 院号:「○○院」。家・地域への貢献や信仰実践等を総合して授与される尊称。
- 道号:「慈光」「泰然」など、故人の徳・志・人柄を映す語。
- 本体(二字):仏弟子名の中核。意味の整合と全体の調和が重視される。
- 位号:性別・年齢の目安を示す称。地域差あり。
補足用語:授戒=戒を受ける儀礼/寿戒名=生前に授かる戒名/過去帳=寺院が物故者名を記す台帳。相談・見積時に頻出するため意味を押さえておきましょう。
真言宗における戒名の位置づけと意義
真言宗では、戒名は仏弟子としての帰依の証であり、故人を敬い、家族が祈りを捧げる際の拠りどころになります。戒名は一回限りの葬儀だけで完結せず、初七日・四十九日・一周忌以降の年忌法要でも読み上げられ、供養の継続性を担保します。
構成要素(院号・道号・本体・位号)は「格付けの装飾」ではなく、故人像の言語化と理解すると、寺院との対話がスムーズです。表記は位牌・過去帳・墓碑で統一し、旧字/新字体・読みの最終確認を清書前に行うと後悔がありません。
戒名が使われる場面と必要性(位牌・過去帳・墓碑・法要)
戒名は次の局面で実務的に用いられます。法的手続きは俗名で進められますが、仏式の場面では戒名が前提です。
- 通夜・葬儀・初七日:読経や祭壇掲示、弔辞・返礼文の記載。
- 位牌・過去帳:戒名・没年月日・俗名併記の要否、字体の統一確認。
- 墓碑・納骨:刻字内容(戒名/俗名併記)、家の先例との整合、字詰め。
- 年忌法要:読み上げ表記の標準化(誤読・表記揺れを防ぐ)。
実務のコツは、「最終表記の見本」を清書前に確認し、家族・寺院・石材店・葬儀社で共有すること。これにより、表記揺れによる再刻・再書写や追加費用を未然に防げます。
真言宗の戒名の構成と種類(院号・道号・戒名本体・位号)
-e1755607459844.webp)
真言宗の戒名は、一般に院号・道号・戒名本体(二字)・位号の四要素で構成されます。すべて必須ではなく、寺院の方針や地域慣習、家の先例、そしてご家族の意向で組み合わせが決まります。
構成は“格上げの装飾”ではなく、故人像を言語化して供養に活かす設計と捉えるのが要点です。なお費用(値段)は要素数よりも、院号の有無や儀式範囲、校正や書写の手間、移動の有無など実務条件で左右されます。
院号の意味と授与基準|ランクの考え方
院号は「○○院」の尊称で、地域や寺院への貢献、信仰実践、家の先例などを総合して授与されることが多い要素です。一般に院号が付くと上位ランクと受け止められ、値段は上振れしやすいものの、必須ではありません。
大切なのは「院号が故人像と供養方針に合うか」。迷う場合は、付与基準・費用差の根拠・不付与の理由を面談で確認し、家族の合意とともにメモ化しておくと後日の齟齬を防げます。年忌などの追善に回す予算との配分も同時に検討しましょう。
道号の役割と選び方(人柄・徳目の表現)
道号は徳や志、人柄を表す部分で、「慈光」「妙心」「泰然」など仏語・美称から選ばれます。選定では読みやすさ・誤読の少なさ・旧字/新字体を事前に確認し、候補を複数案(同義語・近義語)で比較すると納得度が上がります。
数字条件(例:6文字)を重視する場合も、まずは「道号+本体二字」のバランスと響き、位牌や墓碑での見え方を優先。清書前に下書き(校正)を出してもらえるか、修正可否と費用の取り扱いも合わせて確認しておきましょう。
戒名本体(二字)と位号の種類・並び順
戒名本体(二字)は仏弟子としての名の中核で、意味の整合と全体調和が重視されます。末尾の位号は年齢・性別などの目安を示す称で、価格への影響は寺院運用により異なり、院号ほど明確な差が出ないこともあります。
一般的な並びは院号 → 道号 → 本体(二字) → 位号。表記は位牌・過去帳・墓碑で統一し、読みや字体(旧字/新字体)を清書前に確定します。
- 居士/大姉:成人の高位の称とされることが多い。
- 信士/信女:成人の一般的な称。
- 童子/童女・嬰児:子ども・乳幼児に用いる表現(地域差あり)。
まとめると、構成は「多いほど良い」ではなく、故人の尊厳と家族の納得を基準に決めるのが最良です。費用面では院号の有無が主な変動要因になりやすいため、寺院の基準と内訳を確認し、表記は必ず最終見本でチェックしてから清書に進みましょう。
真言宗 戒名 値段相場一覧|院号・ランク・位号別
ここでは、真言宗の戒名の値段を「院号の有無」と「位号」の観点で読み解くための目安レンジを示します。実額は寺院方針・地域差・檀家関係・儀式範囲で上下します。必ず内訳と条件をそろえて比較する前提でお使いください。
【一覧】院号なし(信士・信女/居士・大姉)の目安
院号なしで成人の信士・信女の場合、目安は5〜15万円程度。居士・大姉は10〜15万円台がよく語られるレンジです。
もっとも、道号の付与、文字の校正回数、旧字指定、位牌・過去帳の記入といった実務の手間で前後します。例として、一日葬(僧侶1名・読経2回・交通費別)+院号なし+信士/信女は、費用を抑えつつ整った供養になりやすい構成です。
【一覧】院号あり(上位ランク)の目安と幅
院号あり(○○院)は一般に数十万円台が中心レンジです。授与の可否や基準(家の先例、地域社会への貢献、信仰実践など)に裁量があり、儀式範囲(通夜の有無、僧侶数、読経回数)、書写仕様(奉書・色紙、浄書の手間)でも幅が出ます。
判断のコツは、付与理由の説明と費用差の根拠を事前に確認し、追善供養(年忌)への配分と合わせて全体最適で考えることです。
凡例と前提条件(内訳の揃え方・地域差の見方)
相場比較は「金額」より条件の統一が命です。次の凡例を決めてから各寺院に同条件で問い合わせると差が明確になります。
- 儀式範囲:通夜の有無/一日葬・火葬式/僧侶人数/読経回数。
- 戒名取扱い:院号・道号の可否、下書き(校正)の有無、旧字指定。
- 費用区分:読経料・戒名料・お車代・御膳料・交通宿泊の扱い(総額か分離か)。
サンプル凡例:「院号なし/成人・信士(信女)/一日葬/僧侶1名/読経2回/交通費別」。この条件で内訳・総額・適用条件を文章で受け取り、家族で共有すれば、地域差や寺院方針によるブレを納得して比較できます。
【文字数】6文字の戒名は可能?数え方と注意点
検索の多い「6文字の戒名」は、真言宗でも実現可能です。ただし、文字数の数え方は全国統一ではなく、寺院(地域)ごとの基準で運用されています。
まず「どこまでを数えるのか」を合意し、そのうえで読みやすさ・表記統一・位牌や墓碑での見え方まで含めて確認するのが実務的です。数字だけに引きずられず、意味の整合と全体バランスを優先しましょう。
6文字の数え方(道号+本体/院号・位号の扱い)
多くの寺院では、道号+戒名本体(二字)を合計して「〇文字」と呼び、院号(○○院)と位号(居士・大姉・信士・信女)は文字数に含めない扱いが一般的です。たとえば「慈光(四字)+□□(二字)=6文字」という考え方です。一方で、運用が異なる寺院もあるため、事前に「院号・位号はカウント外で良いか」「道号は何字まで想定か」を必ず確認してください。
- 例1:道号「妙心」(二字)+本体「□□」(二字)=4文字(6文字に満たない)
- 例2:道号「慈光明」(三〜四字想定)+本体(二字)=5〜6文字
- 確認要点:読み(音読み/訓読み)、旧字/新字体、連綿体の有無
「6文字」を強く希望する場合は、道号の候補を複数出してもらい、読みやすさと語義の適合で選ぶと合意が早まります。
文字数と値段の関係・誤解しやすいポイント
しばしば「文字数が増えると値段も上がる」と誤解されますが、費用に効くのは主に院号の有無(ランク)や儀式範囲、書写の手間・移動費などの実務条件です。
文字数そのものが直線的に価格へ反映されるとは限りません。ただし、下書き(校正)回数の増加、旧字指定や特殊書体、位牌・墓碑の刻字調整など、付随作業が増えると追加費用が生じることはあります。
- 費用は「平均額」ではなく内訳(読経料・戒名料・お車代等)で確認
- 「6文字=高額」という固定観念は捨て、根拠の説明を受けて判断
- 校正の有無・回数と修正時の取り扱いを先に合意
読みやすさ・表記統一・レイアウトの実務
数字条件より大切なのは、供養の現場で美しく読みやすいことです。位牌や過去帳、墓碑の刻字では、字面の詰まり・縦画の密度・長体/平体のバランスで見え方が大きく変わります。清書前に最終レイアウトの見本(書写サンプル・刻字イメージ)を確認し、旧字/新字体や並び順を家族・寺院・石材店で統一しましょう。
- チェック1:読みやすさ(誤読の恐れ、似た字形の混在)
- チェック2:表記統一(位牌・過去帳・墓碑で同一の字体・並び)
- チェック3:校正プロセス(清書前の確認、修正可否と費用)
最終的な判断軸は、故人の人となりが伝わるか/供養の場で違和感がないかです。「6文字」は目的ではなく手段。真言宗の作法に沿いつつ、家族が納得できる表現を寺院と対話的に整えていきましょう。
戒名の付け方(真言宗)|決め方の流れとコツ
|決め方の流れとコツ-e1755607782426.webp)
初めての方ほど、順序を押さえるだけで迷いが激減します。真言宗の戒名は、寺院との対話で〈人柄・歩み〉を言語化し、位牌・過去帳・墓碑など実務へ落とし込む作業です。
ここでは、面談準備→候補提示・校正→清書の基本線を解説し、併せて生前戒名(寿戒名)と逝去後の違い・注意点をまとめます。数字(6文字)や“格”に偏らず、意味・読み・見え方を最優先に進めましょう。
菩提寺への相談準備(略歴・先例・希望の整理)
面談前に、寺院が判断しやすい材料を1枚に集約します。必須は次の通りです。
- 略歴・人柄:生年・職業・地域活動・性格や大切にした価値観(短文で可)。
- 家の先例:親族の戒名の控えや位牌写真(表記統一の指標)。
- 希望の軸:院号の可否、位号の想定、道号で表したい徳目、6文字など文字数方針。
- 実務条件:儀式範囲(通夜の有無・僧侶人数・読経回数)、予算の上限、刻字対象(位牌/墓碑/過去帳)。
- 表記指定:旧字/新字体、読み(ふりがな)、連絡先と日程候補。
提出は紙一枚またはメールで。比較のための凡例(例:院号なし/僧侶1名/読経2回/交通費別)を明示すると、費用や構成の相談がすぐ本題に入れます。
候補提示→下書き(校正)→清書のプロセス
多くの寺院では、ヒアリング後に戒名案が提示されます。ここで重視するのは意味の整合・読みやすさ・全体の調和(院号・道号・本体二字・位号のバランス)です。
- 候補比較:道号は同義・近義を複数案提示してもらい、誤読の恐れや字面の詰まりをチェック。
- 下書き(校正):清書前に必ず紙面画像等で確認。位牌・過去帳・墓碑で同じ表記になるかを同時に判定。
- 清書・納品:奉書や色紙への書写、朱印の有無、受け渡し方法を合意。最終版は写真で保管。
合意は口頭で終えず、「最終表記・修正条件・費用」をメールや書面で残します。校正回数や旧字指定が費用に影響する場合があるため、根拠の説明を受けてから決定しましょう。
生前戒名(寿戒名)と逝去後の違い・注意点
生前戒名(寿戒名)は、本人の意向を反映しやすく、読み・字体・並びを時間をかけて整えられる利点があります。費用は寺院方針により、葬儀時と同等〜取り扱い差が出ることもあるため、授戒の有無・納品形式・将来の修正可否まで確認しましょう。
逝去後に授かる場合は、枕経や式場手配と並行して短時間で決める必要があり、家の先例・希望の軸・表記方針を事前にメモ化しておくと迷いを減らせます。
- 寿戒名の注意:将来、位号や院号の変更可否、過去帳・墓碑更新の扱いを確認。
- 逝去後の注意:日程優先で決めた項目は、四十九日までに最終確認して表記統一。
- 共通:数字条件(6文字)は手段。故人像が伝わるかを判断軸に。
要は、準備→校正→記録の3点を外さないこと。これだけで、初めてでも納得度の高い戒名決定が可能になります。
よくある質問Q&A
初めての方が迷いやすいポイントを、真言宗・戒名・値段・6文字・院号(ランク)の観点で簡潔に整理しました。詳細は各章に譲りつつ、ここでは「まず何を確認すればよいか」に絞って答えます。
Q: 真言宗の戒名の値段はどう決まる?
A: 価格は平均額よりも、前提条件(内訳と範囲)で大きく動きます。主な決定要因は次の三つです。
- 院号(ランク)の有無:「○○院」が付くと上振れ傾向。必須ではありません。
- 儀式範囲:通夜の有無、僧侶人数、読経回数、会場(寺・式場・自宅)。
- 付帯費用と実務:お車代・宿泊、書写の手間、校正回数、旧字指定など。
比較のコツは、「何が含まれて、何が別包みか」を最初に文章で確認すること。たとえば「院号なし/僧侶1名/読経2回/交通費別」という凡例を固定し、同条件で見積を集めると差の理由が見えます。
Q: 6文字の戒名は指定できる?数え方の基準は?
A: 指定は可能です。ただし文字数のカウントは全国統一ではなく、寺院ごとの運用差があります。多くは道号+本体(二字)を数え、院号・位号は含めない扱いです。実務では次を合意しましょう。
- 数える範囲:「道号+本体=6文字」で良いか、院号・位号は除外で良いか。
- 候補の幅:道号は同義・近義で複数案を出してもらい、読みやすさで選定。
- 校正と統一:清書前の下書き確認、位牌・過去帳・墓碑の表記統一。
なお「6文字だから高額」という直結はありません。費用に効くのは主に院号の有無や儀式範囲・校正回数などの実務条件です。
Q: 生前戒名(寿戒名)や院号のランク変更は可能?
A: 寿戒名(生前)は可能で、本人の意向を反映しやすい利点があります。費用は寺院によって、葬儀時と同等〜取り扱い差が出ることもあるため、授戒の有無・納品形式・将来の修正可否まで確認を。
院号の追贈(後日付与)や構成変更は、寺院方針・地域慣習・家の先例で可否が分かれます。可能な場合は、位牌・過去帳・墓碑の更新範囲、必要な儀礼、費用と手順を事前合意し、新旧表記を文面で確定してから進めると安全です。
まとめ|真言宗の戒名と値段を理解し、納得のいく選択を
本記事では、真言宗の戒名の値段を左右する主要因(院号の有無=ランク、位号、地域差・寺院方針・儀式規模)と、構成の種類(院号・道号・本体二字・位号)、さらに「6文字」の数え方、実務の進め方(戒名の付け方)を整理しました。
平均額に頼るより、内訳と条件をそろえて比較し、清書前の下書き(校正)確認と表記統一までをワンセットで進めるのが失敗しないコツです。最後に、今日から動けるチェックとアクションをまとめます。
今日決めることチェックリスト
- 価値観と予算の軸(院号の可否/年忌へ回す配分)を家族で共有した
- 構成の希望(院号・道号・本体二字・位号/6文字の扱い)をメモ化した
- 家の先例(親族の戒名)・位牌写真を収集し、表記の指標を用意した
- 凡例条件(例:院号なし/僧侶1名/読経2回/交通費別)を仮決めした
- 菩提寺(または相談先)へ連絡する日程と連絡手段を決めた
寺院へ確認すべき三点(内訳・校正・表記統一)
- 内訳と条件:読経料・戒名料・お車代・御膳料・交通宿泊の扱い/儀式範囲(通夜の有無、僧侶人数、読経回数)
- 校正プロセス:清書前の下書きの有無、修正可否と費用、旧字・新字体や読みの指定
- 表記統一:位牌・過去帳・墓碑での並び順(院号→道号→本体→位号)と最終レイアウトの確認方法
次のアクション:見積り取得→下書き確認→清書
- STEP1 見積り取得:決めた凡例で問い合わせ、同条件の見積りを文章でもらう(「何が含まれ、何が別包みか」を明記)
- STEP2 下書き確認:候補案の意味・読み・バランスを家族でチェック。6文字の数え方や道号候補の代替も同時に確認
- STEP3 清書・表記統一:合意内容をメールで確定し、位牌・過去帳・墓碑の最終表記を統一してから清書へ
数字や“格”に偏らず、故人の尊厳と家族の納得を中心に据えれば、真言宗の戒名はきっと良い形に整います。迷った点は必ず寺院に確認し、記録を残す――それが納得のいく選択への最短ルートです。