お悔やみの言葉への返事マナー|メール・LINE・ビジネス別例文集

「お悔やみ申し上げます」と声をかけられたとき、どんな言葉で返事をするのが正解なのか、すぐに思いつかない方も多いでしょう。短すぎても素っ気なく、長すぎても場にそぐわない――そんな難しさがあるのがお悔やみ返事のマナーです。
本記事では、一般的な返答例からメールやLINE、職場での対応まで、状況別にポイントを整理しました。

お悔やみの言葉をいただいたときの基本的な返事の考え方
大切な人を亡くされた直後は、心身ともに大きな負担を抱えており、周囲から寄せられる「お悔やみの言葉」にどう返事をすればよいか悩む方も多いものです。特に初めて葬儀を取り仕切る立場になると、形式的なマナーや適切な言葉選びに不安を感じやすいでしょう。
基本的に、お悔やみに対する返事は長々と説明する必要はなく、短く丁寧に感謝を伝えることが大切です。相手はご遺族の悲しみに寄り添うために言葉をかけているため、深く踏み込んだ説明や長文のお礼を返すよりも、「お気遣いありがとうございます」「ご丁寧なお言葉をいただき感謝いたします」といった簡潔な言葉で十分です。
また、返事をする際には以下の点に注意しましょう。
- 形式にこだわりすぎず、気持ちを込めて伝える
- 「悲しい」「つらい」といった個人的感情を長々と述べない
- お悔やみに対しては「ありがとう」「感謝いたします」が基本
例えば、葬儀の受付や会場で直接声をかけられた場合には、深々とお辞儀をし「ありがとうございます」とだけ返せば問題ありません。葬儀中に長く会話するのはかえって場の雰囲気を乱すこともあるため、返事は簡潔にとどめるのがマナーです。
お悔やみに対する返事でよく使われる言葉
ここでは、実際に多く用いられる「お悔やみの言葉」への返事の仕方を具体的に紹介します。相手の言葉に対してどのように返すのが適切か、場面ごとにイメージできるよう整理しました。
「お悔やみ申し上げます」への返答例
最も一般的に使われるのが「お悔やみ申し上げます」という言葉です。これに対しては、以下のように返すのが適切です。
- 「ご丁寧なお言葉をありがとうございます」
- 「お気遣いいただき、心より感謝申し上げます」
深い返答を考える必要はなく、感謝の意を一言で示すことが大切です。例えば、遠方から駆けつけてくださった方には「わざわざお越しいただきありがとうございます」と加えると、相手に誠意が伝わります。
「ご愁傷様です」と言われたときの返し方
「ご愁傷様です」は、弔事でよく使われる定型的なお悔やみの言葉です。この場合の返事は、短く頭を下げ「ありがとうございます」と述べれば十分です。余計な言葉を加えるよりも、シンプルな感謝の一言が場にふさわしいとされています。
もし職場の上司や取引先の方から言われた場合には、「恐れ入ります。お気遣いありがとうございます」と少し改まった表現にすると、ビジネスの場面でも失礼になりません。
お悔やみのお礼に返す言葉の基本
葬儀後、メールや手紙でお悔やみをいただいた場合には、改めてお礼を伝えるのが一般的です。このときの文章は、形式を守りつつ簡潔にまとめることが求められます。
例えば、お悔やみメールに対する返信では次のような表現が適しています。
- 「このたびはご丁寧なお悔やみをいただき、誠にありがとうございました」
- 「温かいお言葉を賜り、深く感謝申し上げます」
注意点としては、悲しみを強調しすぎる言葉や、今後の詳細な近況報告などは控えることです。相手は慰めの気持ちを伝えているため、返事も感謝を中心にまとめるのが望ましいでしょう。
こうした言葉を押さえておけば、葬儀の場面やその後のお礼のやり取りでも安心して対応できます。
\無料の資料請求は下記から/
メールやLINEでのお悔やみの返事マナー
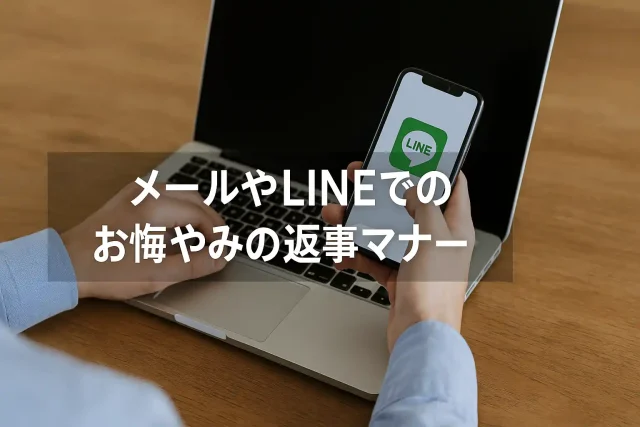
近年では、お悔やみの言葉をメールやLINEなどのメッセージアプリで受け取るケースも増えています。特に遠方に住んでいる方や、急ぎで気持ちを伝えたい場合に利用されることが多いですが、返事の仕方には配慮が必要です。
直接顔を合わせる場面と異なり、文章で気持ちを伝えるため、丁寧さと簡潔さのバランスが求められます。
お悔やみメールをもらったらどう返す?
お悔やみのメールを受け取った場合、できるだけ早めに返信することが望ましいとされています。長文を書く必要はなく、相手のお気遣いに対して感謝の意を示すことが大切です。
例えば、次のような返信が一般的です。
- 「このたびはご丁寧なお言葉をいただき、誠にありがとうございました」
- 「温かいお気遣いをいただき、心より感謝申し上げます」
メールの場合は形式を重んじる場面が多いため、句読点や敬語を正しく使い、落ち着いた文章を心がけましょう。特にビジネス関係の相手から届いた場合は、「ご厚情に深く感謝申し上げます」といったフォーマルな表現を選ぶと安心です。
LINEで返す際の注意点と例文
親しい友人や同僚からLINEでお悔やみをいただくケースも増えています。LINEでは気軽なやり取りが一般的ですが、葬儀や訃報に関わるやり取りでは、スタンプや絵文字を使うのは控えるのがマナーです。
実際の返信例としては以下のようなものが挙げられます。
- 「ご連絡ありがとうございます。お気遣いいただき感謝しています」
- 「温かい言葉をありがとう。落ち着いたら改めて連絡させていただきます」
LINEでは即時性が高いため、返事が遅くなると相手に不安を与えることもあります。返せない状況でも、ひとまず「お気遣いありがとうございます」とだけ返信しておくと良いでしょう。
お礼の返信で避けたい表現
メールやLINEでの返事で注意したいのは、相手の言葉に対して過度に感情的になったり、不適切な言葉を使ってしまうことです。以下のような表現は避けるようにしましょう。
- 「どうしてこんなことになったのか分かりません」など、悲しみを強調しすぎる言葉
- 「またすぐ会いましょう」といった場にそぐわない軽い表現
- 絵文字・顔文字・スタンプなどカジュアルすぎる要素
相手は慰めや励ましの気持ちを伝えているため、返事もそれに応える形で「感謝」を中心にまとめることが適切です。形式ばった言葉よりも「ありがとうございます」と誠実に伝えることが、結果として最も失礼のない対応になります。
このように、メールやLINEでのお悔やみ返事は、対面の場面よりも言葉選びに注意が必要です。文章で伝える分、簡潔さと丁寧さを意識し、相手への感謝の気持ちを大切にしましょう。
\無料の資料請求は下記から/
ビジネス・職場関係でのお悔やみ返事
仕事上の関係者から「お悔やみの言葉」をいただくことは多くあります。上司や取引先、同僚など、相手との立場や関係性によって適切な返事の仕方は少しずつ異なります。葬儀の場面やその後のメール・手紙でのやり取りにおいて、礼儀を守りつつ、感謝の気持ちを簡潔に伝えることが最も重要です。
ここでは、職場やビジネス関係でよくあるシーンごとに、返事の仕方や実際の例文を紹介します。
上司や取引先からのお悔やみに対する返事
上司や取引先といった目上の方から「お悔やみ申し上げます」と言われた場合は、より丁寧で改まった返事を心がける必要があります。軽い言葉や簡単すぎる返事では失礼にあたるため、謙虚な姿勢を示すことが大切です。
例文としては次のようなものが適切です。
- 「ご丁寧にお言葉をいただき、誠にありがとうございます」
- 「ご多忙のところ、お気遣いを賜り深く感謝申し上げます」
もし取引先から弔電やお花をいただいた場合には、葬儀後に改めて礼状を送るのが望ましいでしょう。その際も「このたびはご厚情を賜り、心より御礼申し上げます」といった表現がよく用いられます。
同僚や部下からのお悔やみに対する返事
同僚や部下といった社内の関係者に対しては、形式ばかりにとらわれず、感謝を率直に伝えることが重要です。距離感が近い分、形式的すぎるよりも温かさを込めた返事のほうが自然に受け取られます。
例えば以下のような返事が考えられます。
- 「ご心配いただきありがとうございます。お気持ちに感謝しています」
- 「このたびは温かい言葉をいただき、励まされました」
社内では顔を合わせる機会も多いため、直接伝える場合は深々とお辞儀をしながら「ありがとうございます」とだけ言えば十分です。業務に戻る際の気遣いにもつながります。
社内メールでの返答例
職場では、葬儀に出席できなかった人から社内メールでお悔やみをいただくこともあります。メールでの返事は、あまり長くならず簡潔にまとめるのが適切です。件名は「御礼」や「お心遣いありがとうございます」とし、本文は2〜3行で十分です。
例文:
- 「このたびはご丁寧なお言葉をいただき、心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。」
- 「温かいお気遣いをいただき、誠にありがとうございました。お心にかけていただいたこと、大変ありがたく存じます。」
社内メールでは、ビジネス文書の形式を保ちながらも堅苦しすぎない表現を意識することがポイントです。特に部署内や親しい関係の同僚には「お気遣いいただきありがとうございます」といった柔らかい表現を使うと良いでしょう。
このように、ビジネスや職場関係でのお悔やみ返事は、相手との関係性に応じた言葉選びが求められます。上司や取引先には改まった表現を、同僚や部下には温かみのある言葉を使い分けることで、社会人としてのマナーを守りつつ誠実さを伝えることができます。
お悔やみの返事で気をつけたいマナーと注意点
お悔やみに対する返事は、相手への感謝を伝える大切な行為ですが、言葉選びや対応の仕方を誤ると、かえって失礼に受け取られてしまうことがあります。特に葬儀は宗教や地域によって習慣が異なるため、場に応じた配慮が欠かせません。ここでは、返事をするときに注意すべきマナーや避けたいポイントを具体的に解説します。
宗教や習慣による言葉選びの違い
日本の葬儀は仏式が中心ですが、神道やキリスト教など、宗教によって適切な言葉は異なります。例えば仏式では「ご冥福をお祈りします」が一般的ですが、浄土真宗では「冥福」という考え方がないため不適切とされています。そのため返事でも「ご丁寧にありがとうございます」と宗教色を含まない表現にとどめる方が無難です。
また、神道では「御霊の安らかならんことを」など独自の言い回しがあり、キリスト教では「安らかなお眠りを」などが使われることもあります。返事の際は相手の宗教に合わせる必要はありませんが、特定の宗教的な表現を避け、感謝を軸にすると安心です。
返事を控えた方がよいケースとは
すべてのお悔やみに必ず返事をする必要があるわけではありません。例えば、会場で多くの弔問客から声をかけられる場合、一人ひとりに長く返事をしていると式の進行を妨げてしまいます。その場合は、軽く会釈やお辞儀をして「ありがとうございます」とだけ伝えるのが適切です。
また、SNSで知人からコメントをもらった場合などは、必ずしも返信を求められているわけではありません。精神的に余裕がないときは無理に返事をせず、後日落ち着いてから「ご心配いただきありがとうございました」とまとめて伝える方法もあります。
避けるべき具体的な言葉や行動
お悔やみに返事をする際、以下のような言葉や行動は避けるべきです。
- 「頑張ります」「早く立ち直ります」など自分の決意を強調する言葉
- 「長生きしてほしかった」など故人への未練を強く述べる表現
- 冗談や軽い言葉、絵文字・スタンプを使った返答(特にLINEの場合)
相手は遺族の気持ちを思いやって声をかけているため、返事も「ありがとうございます」「感謝いたします」といった誠実な言葉が最適です。
さらに注意したいのは、返事を長文にしすぎないことです。葬儀の場やその後のやり取りは、あくまで弔意を示すことが目的であり、近況報告や世間話を加えると不適切になります。返事は短く簡潔に、相手への感謝を第一にすることを意識しましょう。
このように、お悔やみに対する返事は相手の立場や場面に応じて柔軟に対応することが求められます。宗教や習慣の違いに配慮しつつ、不必要な言葉を避けることで、失礼のない誠実な返事ができます。
\無料の資料請求は下記から/
まとめ:お悔やみの言葉への返事は感謝と簡潔さが基本
お悔やみの言葉をいただいたとき、多くの方が「どう返せば失礼にならないか」と悩みます。しかし、基本はとてもシンプルで、相手の気持ちに感謝を伝え、短く丁寧に返すことが大切です。
対面であれば深くお辞儀をして「ありがとうございます」とだけ述べれば十分ですし、メールやLINEであれば「ご丁寧なお言葉をいただき、感謝申し上げます」と一言添えるだけで気持ちは伝わります。形式や長さにとらわれる必要はなく、むしろ簡潔にまとめる方が誠意が伝わりやすいものです。
また、ビジネス関係では上司や取引先には改まった表現を、同僚や部下には温かみを込めた言葉を選ぶなど、相手との関係性に合わせて表現を工夫することが望まれます。さらに、宗教や習慣によっては使わない方がよい表現もあるため、できるだけ宗教色を避け、誰にでも使える感謝の言葉を選ぶと安心です。
お悔やみに対する返事は、遺族にとって大きな負担にならないよう配慮されている場面も多いため、無理に長文を書く必要はありません。お礼の気持ちを一言添えるだけで、相手の心には十分に伝わります。
つまり、「感謝」と「簡潔さ」を意識することが、どんな状況でも通用する最良のマナーです。これを押さえておけば、初めての葬儀であっても落ち着いて対応できるでしょう。