曹洞宗の葬儀でお布施はいくら?相場・書き方・渡し方を徹底解説

「曹洞宗のお葬式でお布施はどのくらい必要?」「封筒の裏には何を書く?」──こうした疑問は喪主やご家族にとって大きな不安のひとつです。
本記事では、葬儀で必要となるお布施の相場から、封筒の選び方・書き方、渡し方のマナーまで、実際に役立つ知識を整理しました。

曹洞宗の葬儀におけるお布施の相場はどのくらい?
曹洞宗の葬儀で最も気になる点のひとつが「お布施の相場」です。お布施とは、僧侶に読経や戒名授与をお願いした謝礼の意味を持つもので、料金表のように一律で決まっているわけではありません。
あくまで感謝の気持ちを形にしたものですが、実際には地域や寺院ごとの慣習により目安となる金額があります。
一般的に、曹洞宗の葬儀で僧侶を招いた場合のお布施相場は以下のとおりです。
- 通夜・葬儀一式のみ:20万円〜30万円程度
- 戒名授与を含む場合:30万円〜50万円程度
- 初七日法要までお願いする場合:40万円〜60万円程度
例えば、地方の檀家制度が根付いている地域では、檀家として日頃から寺院にお布施や寄付をしている分、葬儀時のお布施が相場より低めになることもあります。
一方で、都市部で檀家になっていない場合や、臨時で僧侶を依頼する場合には、相場がやや高めになる傾向があります。いずれにしても、「相場に沿いつつ、経済状況や地域慣習を踏まえて無理のない範囲で準備する」ことが大切です。
\無料の資料請求は下記から/
曹洞宗の葬儀でお布施が必要となる場面
曹洞宗の葬儀では、通夜から初七日法要まで複数の場面で僧侶に読経や法要を依頼します。その都度お布施を渡すのではなく、まとめて一包みにして渡すのが一般的です。ここでは、代表的なお布施が必要となる場面を整理します。
通夜や葬儀式でのお布施
通夜と葬儀式は曹洞宗の葬儀において中心的な儀式です。通夜では故人を偲び、読経を通じて遺族や参列者が心を整える役割があります。
葬儀式では僧侶による読経・引導法語(故人を悟りの世界へ導く説法)が行われます。これらの儀式に対する謝礼としてお布施を包みます。
地域によっては通夜と葬儀式を分けず、一連の流れとしてまとめてお布施を渡す場合もあります。金額は先に述べたように20万円前後からが目安となります。
戒名料や読経料との関係
曹洞宗の葬儀では、多くの場合「戒名(かいみょう)」を授かります。戒名とは、故人が仏門に帰依した証として授けられる名前で、葬儀や法要で用いられます。
戒名料はお布施に含まれる形で包むのが一般的で、戒名の位階(居士・大姉・院号など)によって相場が変動します。位が高いほど戒名料が上がり、お布施の合計も高くなる傾向があります。
また、読経料と呼ばれる謝礼もありますが、これもお布施の中にまとめて含めるのが基本です。別途用意する必要はなく、総額として僧侶にお渡しすれば問題ありません。
初七日法要まで含める場合
曹洞宗では、葬儀直後に「初七日法要」を営むことがあります。これは故人が亡くなって七日目に行う法要ですが、近年は遺族の負担を考えて、葬儀当日に繰り上げて実施されることが多いです。
この場合、僧侶に追加で読経をお願いするため、お布施の総額も数万円から十万円ほど上乗せされるケースがあります。
たとえば「葬儀+初七日を同日に行うプラン」では、相場として40万円〜60万円程度が必要になります。寺院によっては初七日の分を別封筒に分けるよう指示されることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
お布施の正しい書き方と封筒の選び方
お布施は金額だけでなく、封筒の種類や表書き、裏面の記載方法も重要です。特に初めて葬儀を行う場合には、「どの封筒を使えば良いのか」「書き方に決まりはあるのか」と悩む方も少なくありません。ここでは曹洞宗の葬儀における基本的なマナーを整理します。
表書きは「御布施」と書くのが基本
お布施の表書きは、宗派を問わず「御布施」と書くのが一般的です。毛筆や筆ペンを用いて縦書きで記入し、楷書で丁寧に書くのが望ましいとされています。印刷された封筒を使用する場合でも、できれば手書きで加筆すると気持ちが伝わりやすいでしょう。
なお、香典袋とは異なり、お布施袋に不祝儀袋のような黒白や双銀の水引は不要です。無地の白封筒、または仏事用に販売されている「御布施」と印字された封筒を選ぶのが適切です。
封筒裏に住所と氏名を記入する理由
封筒の裏面には、施主の住所と氏名を記入します。これは僧侶や寺院が誰からのお布施なのかを把握するために必要です。特に檀家でない場合、寺院側にとって施主の情報が記録として残るので、後日の法要依頼やお礼状のやりとりがスムーズになります。
記入は黒のペンや毛筆を使い、中央下部に縦書きで書くのが基本です。住所は省略せず、正式に記載することで丁寧さを示せます。
中袋の使い方と金額の書き方
お布施には中袋を用いる場合があります。中袋を使用する場合は、表面に金額を漢数字で記入し、裏面に住所と氏名を書きます。金額は「壱萬円」「伍萬円」などの旧字体で記載すると、より正式な印象になります。
一方、寺院によっては「中袋不要」とされることもあり、その場合は直接封筒に現金を入れて問題ありません。迷ったときは葬儀社や寺院に確認すると安心です。
\無料の資料請求は下記から/
曹洞宗の葬儀でのお布施の渡し方マナー
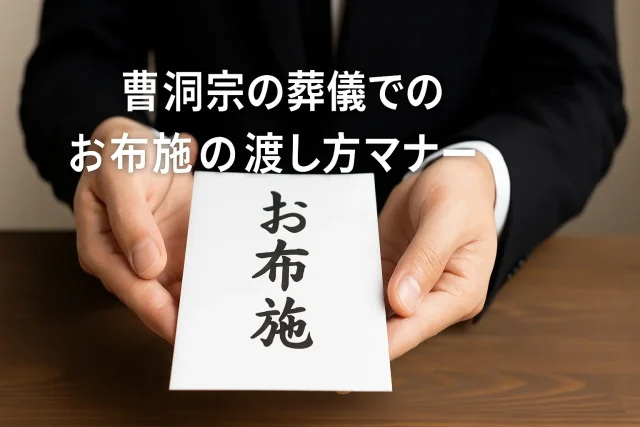
お布施は金額や封筒の準備だけでなく、渡し方にもマナーがあります。正しい方法を理解しておくことで、僧侶や寺院に失礼のない形で気持ちを伝えることができます。
僧侶に直接渡すのか寺院に渡すのか
お布施は基本的に法要を終えたあと、僧侶に直接手渡すか、寺院に預けるのが一般的です。葬儀社が仲介する場合もあり、その際は受付や式後に葬儀社の担当者から僧侶に渡してもらうことも可能です。
直接渡す場合は「本日はどうもありがとうございました」と感謝の言葉を添えて渡すと丁寧です。
袱紗に包んで渡すのが礼儀
お布施はそのまま封筒を裸で持ち歩かず、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが基本です。袱紗は弔事用の紫色や紺色が適切で、渡す際には袱紗から取り出して両手で差し出します。これは「丁寧に心を込めて渡す」という意思表示になります。
タイミングは読経や法要の前後が目安
お布施を渡すタイミングは、読経や戒名授与が終わったあとが一般的です。ただし、葬儀の流れによっては事前に渡すよう案内される場合もあります。タイミングに迷うときは、葬儀社の担当者に相談するのが安心です。
なお、複数の法要(葬儀と初七日など)を同日に行う場合は、一包みにまとめて渡すのが基本です。別々に封筒を準備する必要があるかどうかは、事前に寺院へ確認しておきましょう。
お布施を準備する際の注意点と実務的なポイント
お布施は「相場に沿って金額を用意する」だけでなく、渡す際の配慮や実務的な準備も大切です。特に初めて葬儀を執り行う方は、細かな点で迷うことが多いものです。ここでは注意しておきたいポイントを具体的に紹介します。
相場より多い・少ない場合の考え方
相場はあくまでも目安であり、必ずその金額にしなければならないわけではありません。例えば経済的に余裕がある場合や、寺院との関わりが深い場合には相場より多めに包むケースもあります。
反対に、家計の状況や喪主の立場によっては、相場よりやや少なめにお布施を渡すこともあります。
大切なのは「金額の多寡よりも感謝の気持ちを込めること」です。寺院側もその点を理解しているので、相場にとらわれすぎず、自分たちに無理のない範囲で準備しましょう。
領収書やお礼状についての対応
お布施は「お金ではなく感謝の気持ちを形にしたもの」という考え方があるため、寺院から領収書を受け取ることは通常ありません。
しかし、葬儀費用の精算や会社への弔慰金精算に必要な場合には、事前に寺院へ相談すれば領収書や受領書を発行してもらえることもあるので、遠慮なく確認しておきましょう。
また、お布施を渡した後にお礼状を出すのも丁寧な対応です。特に檀家でない場合や、遠方から僧侶に来てもらった場合には、簡単なお礼状を送ることで今後の関係も円滑になります。
遠方の僧侶を招く場合の交通費や御車代
葬儀で僧侶を遠方から招く場合は、交通費や移動の負担を考慮し「御車代(おくるまだい)」を別に包むのが一般的です。御車代は数千円から1万円程度が目安ですが、距離や交通手段によってはそれ以上を包むこともあります。タクシーを利用する場合には実費を負担するのが基本です。
さらに、宿泊が必要な場合には「御膳料(ごぜんりょう)」と呼ばれる食事代を渡すこともあります。これは1万円前後が目安で、必ずしも現金でなくても仕出し料理の手配で代えることも可能です。
御車代や御膳料は、お布施とは別封筒に包み、表書きにはそれぞれ「御車代」「御膳料」と記載します。まとめて渡すことは避け、個別に用意するのがマナーです。
以上のように、お布施の準備には金額面だけでなく、領収書やお礼状、御車代などの付随する配慮も欠かせません。事前に葬儀社や寺院に相談しておけば、当日慌てずに対応できるでしょう。
\無料の資料請求は下記から/
まとめ|曹洞宗の葬儀でのお布施は相場を目安に心を込めて準備しよう
曹洞宗の葬儀におけるお布施は、通夜や葬儀式、戒名授与、初七日法要など複数の場面で必要となり、その総額はおおむね20万〜60万円程度が相場です。
金額はあくまでも目安であり、地域の慣習や寺院との関係性によって上下することを理解しておきましょう。
また、お布施の封筒には「御布施」と表書きし、裏面に住所・氏名を記入するのが基本です。袱紗に包んで僧侶へ丁寧に渡すことで、気持ちが伝わりやすくなります。
さらに、遠方から僧侶を招いた場合には、御車代や御膳料を別に用意する配慮も必要です。
お布施に関して不安を抱く方は少なくありませんが、大切なのは金額の多寡ではなく、感謝の心を込めて準備する姿勢です。迷うときは葬儀社や寺院に相談すれば、具体的なアドバイスを得られるでしょう。
初めての葬儀で戸惑う場面も多いかもしれませんが、相場やマナーを押さえておけば、僧侶や参列者に失礼なく対応できます。ご家族の思いを込めたお布施が、故人を見送る大切な供養の一部となることを意識しながら、安心して準備を進めてください。