東京の火葬場ガイド|23区・多摩の公営/民営・料金と選び方

東京の火葬場を探すときにまず知りたいのは「どこが近い・いつ取れる・総額いくらか」です。直葬から一般葬まで、必要書類と予約の進め方、費用の見方をやさしく案内します。
この記事のポイント
東京の火葬場は、近さ・空き・費用の三軸で選べば迷いません。
この記事で分かること
東京は23区と多摩で運営や料金が異なります。
基本の流れは、死亡届→火葬許可証→火葬場予約→当日手続きです。
移動時間を短く、空きは複数同時照会、費用は同条件で比較すると安心です。
要点
結論
東京の火葬場は、公営と民営の火葬施設の総称で、地域や設備により条件と料金が変わる場所です。
進め方(4ステップ)
以下の手順で進めます。
- 死亡届提出
- 火葬許可証受取
- 候補2〜3施設へ同時照会
- 当日受付・火葬・収骨
チェックすべき要点(4つ)
選ぶ時は次の要点を確認します。
- 23区/多摩で条件と料金が異なる
- 公営は市民優遇が明確
- 民営は式場併設で移動が少ない
- 友引前後は予約が混みやすい
要点まとめ|東京の火葬場はこう選ぶ
東京の火葬場は「場所(移動)・空き状況・費用」を同時に確認し、同条件で比較すると失敗を避けやすいです。
まずはご家族の移動負担を最小化できる立地を候補にします。次に希望日の空き状況を複数施設へ同時照会し、最後に火葬料と付帯費用(控室・式場・骨壺など)を同条件で見比べます。葬儀社に一括照会を依頼しつつ、主要施設の公式料金を事前に把握しておくと判断が速くなります。
選定軸:場所・空き・費用の優先順位
優先順位は「①移動時間」「②予約の取りやすさ」「③総額」です。高齢の参列者がいる場合は乗換えの少ない駅近や駐車場の有無を重視します。
予約は友引前後や繁忙期に詰まりやすいため、同時に2~3施設へ空き確認を出すのが現実的です。費用は公営が明朗で抑えやすく、民営は設備・動線・滞在性に優れる一方、控室や式場などの加算で総額が上がりやすい傾向があります(施設ごとの最新料金は各公式サイトを基準に確認します。
例:東京博善の火葬料は普通炉で大人90,000円・区民葬59,600円、2024~2025年時点の公式案内)。
- 移動時間: 自宅・式場→火葬場の所要 — 片道30〜45分以内を目安にします。送迎の動線と駐車台数を事前に確認します。
- 空き状況: 希望日の予約可否 — 友引前後は混雑しやすいです。2〜3施設へ同時照会します。
- 総額: 火葬料+控室・式場など — 公営<民営の傾向があります。骨壺・保管・飲食の有無で差が出ます。
最短スケジュールの見取り図(詳細は後述)
- 死亡届の提出 → 火葬許可証の取得
- 候補火葬場の空き照会(2~3施設)
- 搬送・安置・納棺の段取り確定
- 当日の受付 → 火葬 → 収骨
葬儀社へ一括依頼すれば並行処理が可能です。役所の受付時間や友引の休業日程を踏まえ、候補日を「第2・第3希望」まで用意しておくと調整が早まります。
友引・予約混雑の基本認識
都内の多くの火葬場は友引を休業または縮小運営とし、前後日に予約が集中します。とくに三が日明けや友引明けは混みやすいため、候補日時を広げて同時照会するのが現実的です。
多摩の公営では「市民無料」など利用条件が強く働くため、住所地の施設を第一候補に据えると費用面のメリットが大きくなります(立川市公式・日野市公式、2024~2025年更新)。
東京の火葬場一覧とエリア別の特徴
23区は民営大手と公営が混在し、料金は施設ごとに差があります。多摩は公営中心で住所地の「市民料金(無料含む)」が強く働きます。
都内の主要火葬場は、23区では東京博善(民営・式場併設型)と公営が並立し、多摩は市区町村や一部事務組合の公営が中心です。移動・空き・総額の3点を、「併設式場の有無/控室の使い勝手/駐車場・駅距離」という生活導線で具体化すると比較がしやすくなります。
23区の主な火葬場(公営・民営)と管轄・アクセス
民営(東京博善)
町屋・落合・桐ヶ谷・代々幡・堀ノ内・四ツ木はいずれも式場併設で、火葬から通夜・告別式まで一貫運営が可能です。火葬料(普通炉)は大人90,000円、区民葬59,600円、特別室や特別殯館は高額帯です(落合・桐ヶ谷の料金ページ、2024~2025年公式)。
公営(例)
瑞江葬儀所(江戸川区):火葬料は7歳以上59,600円/都民外71,520円(2022年施行・公園協会の料金表)。
臨海斎場(港・品川・目黒・大田・世田谷の広域組合):骨壺の無料提供など公営ならではの明朗性が特徴。式場等の使用料は2023年基準、2025年に改定告知あり(公式)。
- 式場併設: 同一敷地で通夜・告別式・火葬が完結します。民営は併設が標準で動線が短い一方、式場費の加算で総額が上振れしやすいです。
- 区民葬: 指定葬儀社経由で火葬料が優遇されます。目安は59,600円(東京博善の普通炉)ですが、取扱指定や適用条件の事前確認が必要です。
多摩地域の主な火葬場と選び方の要点
多摩は住所地優遇(市民無料・市民料金)の影響が大きく、まずは故人の住民票所在地の施設を優先検討します。
- 立川聖苑(立川・昭島・国立):市民は火葬料無料。友引を除く毎日9:30~15:00に実施(2024年4月・立川市公式)。
- 八王子市斎場:死亡者が市民なら無料、市外は12歳以上80,000円/12歳未満50,000円(2023年4月・八王子市公式)。
- 日野市営火葬場:市民は無料、市外は大人80,000円・10歳未満50,000円・改葬30,000円(2025年1月改定を含む市公式・関連案内)。
- 住所地優遇: 市民無料・市民料金 — 多摩は無料設定が多いです。判定は死亡時住所が基準です(転出直後は要確認)。
- アクセス: 駅距離・駐車場台数 — 直葬は移動の短距離を重視します。送迎車の導線も確認します。
- 混雑回避: 友引明けの集中を避けます。第2・第3候補日を確保し、複数施設へ同時照会します。
東京博善(民営大手)の施設タイプと特徴
東京博善の6斎場は火葬と式場が同一敷地で、参列導線がシンプルです。控室・休憩室の選択肢が多く、都心アクセス・バリアフリー・駐車場など滞在性に配慮された造りが強みです。
一方で式場費・控室費が積み上がりやすく、区民葬の火葬料59,600円を使っても総額は「式場の有無・規模」で差が広がります(落合・桐ヶ谷ほかの料金ページ)。
- 火葬料(普通炉): 東京博善 — 目安は大人90,000円です。区民葬は59,600円(指定葬儀社経由)を確認します。
- 式場費: 桐ヶ谷(雪/鶴) — 目安は286,000円/440,000円です。会場タイプで差があり、キャンセル規定に注意します。
- 公営例(瑞江): 火葬料 — 都民59,600円・都民外71,520円が目安です。最新の適用区分は公式で確認します。
- 公営例(臨海): 骨壺無料提供等 — 明朗性が高いとされています。式場等の使用料改定告知(2025年)に留意します。
ケーススタディ(直葬の比較)
例①「市民無料の多摩公営」:立川聖苑で市民無料のため、直葬総額はプラン料金+搬送・安置中心で構成されます(2024年4月・立川市公式)。
例②「23区・式場併設の民営」:桐ヶ谷で直葬でも控室費を含めると、公営より総額が上振れしやすい一方、移動ゼロで導線が短く、体力負担を減らせます(2025年料金案内)。
料金・相場・待ち日数の目安
東京の費用は「火葬料+付帯費用(控室・骨壺等)」で総額が決まり、友引前後は待ち日数が伸びやすいです。
費用内訳:火葬料・控室・骨壺など必須/任意の区分
火葬料は必須費用です。これに待合室・控室、骨壺・骨箱、霊安室の保管、搬送費、ドライアイス、式場費(式を行う場合)などが加わります。骨壺や控室は施設・選択肢で価格帯が変わります。
任意費用(飲食、返礼、宗教者へのお礼など)は希望に応じて調整できるため、必須(火葬料・最低限の控室)/任意(アップグレードや飲食等)を切り分けて見積へ反映します。
(数値は施設や時期で変動します。最新は各施設の公式案内や自治体の料金表〔2024〜2025年公表分〕をご確認ください。)
- 火葬料: 炉の使用料 — 公営は市民優遇がある場合があります。民営は一律設定が多く、区分や部屋タイプで差が出ます.
- 控室・待合室: 人数と利用時間で選択 — 平日は時間単位の設定が一般的です。延長料金や飲食の可否を事前に確認します。
- 骨壺・骨箱: サイズ・材質で価格が変動 — 基本品は低額〜中価格帯です。施設手配か葬儀社手配かを確認します。
- 霊安室: 安置は1日単位 — 直葬では利用が増えがちです。夜間搬入の可否を確認します。
- 式場費(任意): 通夜・告別式の会場費 — 会場規模で大きく差が出ます。キャンセル規定を必ず確認します。
公営/民営の費用傾向と総額比較の見方
公営は市民優遇や明朗な基準が多く、民営はアクセスと設備が充実しやすいという傾向があります。総額は、移動距離(搬送/タクシー)・控室の滞在時間・骨壺の選択・式場の有無で上下します。
比較は同条件で行います。人数・控室時間・形式(直葬/一日葬/一般葬)・自宅から火葬場の距離を固定し、「火葬料+控室+骨壺+安置」を積み上げて差を把握します。任意費用は比較から外し、後から加えると判断がぶれません。
予約の取りやすさと友引・繁忙期の傾向
多くの火葬場は友引を休業または稼働縮小とし、前後日に予約が集中します。年末年始や大型連休明け、夏季も混雑しやすいです。目安として、直近1〜3日での予約確保は難しく、3〜5日の幅を持つと確定しやすくなります。
実務上は、第1〜第3候補日と時間帯を用意し、2〜3施設へ同時照会します。直葬は控室の必要時間が短いため確定が進みやすい一方、安置施設の確保を並行すると待機日数を抑えられます。
予約・手続きの流れと必要書類
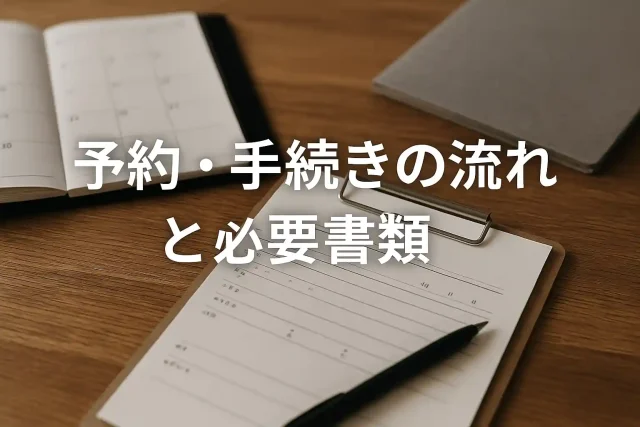
最短化のコツは「死亡届→火葬許可証→予約」を同日内に並行し、搬送・安置・納棺の段取りを先に固めることです。
死亡届と火葬許可証:取得先・必要事項
死亡届は死亡地・届出人の住所地・本籍地の市区町村役所で受理します。医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)と一体になった様式を提出し、火葬許可証が交付されます。
届出人は親族・同居者・家主・後見人などが該当します。身分証と印鑑(自治体により不要の場合あり)を準備し、故人の本籍・住所・氏名・生年月日・死亡日時・死亡地を正確に控えます。役所の開庁時間に依存するため、時間外受付や休日窓口の有無を事前確認します。
- 提出先: 市区町村役所 — 開庁時間内に手続きします。時間外・休日受付の可否を事前に確認します。
- 必要書類: 死亡診断書が添付された死亡届の原本1通。全項目を記入し、誤りは訂正印で訂正します。
- 許可証: 火葬許可証の交付 — 受理当日に交付されるのが一般的です。紛失時は再交付手続きを行います。
- 届出人: 親族等 — 本人確認書類を持参します。届出人と故人の関係性の確認があります。
予約方法:葬儀社経由と個人手配の違い
葬儀社経由は複数施設の同時照会・書類確認・当日の導線設計まで一括で進むため、最短日程の構築に有利です。見積は必須/任意を分離し、控室の利用時間・骨壺の仕様・安置日数を明示して比較します。
個人手配も可能ですが、空き照会・搬送・安置・納棺・当日の受付を自力で連携する必要があり、時間制約や移動手配が負担になります。迷ったら届出と並行で葬儀社に初回相談だけでも入れておくと、キャンセル規定や費用の見通しを早めに把握できます。
当日の受付から収骨までの流れ
当日は予約時間の30〜45分前に現地到着を目安にします。受付で火葬許可証・埋葬許可証(交付一体)を提示し、棺の受け入れ→炉前での拝礼→火葬→収骨の順で進みます。
直葬は控室での待機後、収骨(拾骨)に移ります。高齢の参列者が多い場合は椅子・エレベーター・車寄せの位置を事前確認します。
会葬者が多い場合は集合場所と解散場所を決め、タクシー配車やマイクロバスの待機位置を施設指示に従って調整します。終了後は埋葬許可証の保管を忘れず、納骨までの管理者提出時に備えます。
評判・口コミと注意点(事実と感想を分けて読む)
評判は「立地・設備・導線」が高評価になりやすく、「混雑・時間配分・待合環境」に不満が集まりやすいです。
高評価の傾向:立地・設備・導線
駅から近い、駐車場がわかりやすいなど立地は満足度を左右します。エレベーターやバリアフリー、清潔な控室といった設備も支持されます。特に式場併設タイプは移動が少なく、受付→火葬→収骨までの導線が短い点が評価されます。
口コミでは「高齢の親族が迷わず移動できた」「同一敷地内で完結して負担が少ない」といった声が目立ちます。
一方で、好印象の背景に「平日昼間で空いていた」「少人数の直葬だった」という前提がある場合があります。人数・曜日・時間帯を確認して同条件の評判を参考にすると判断がぶれません。
気になる声:混雑・時間配分・待合環境
火葬は予約制でも友引前後や繁忙期はロビーや控室が混み合います。時間押しが生じると、拾骨や次の移動が詰まり、待機が長く感じられます。待合環境では「座席数」「飲食の可否」「授乳室やおむつ替えスペース」「喫煙動線」などに不満が集まる傾向です。
口コミを読む際は、混雑要因(友引・連休明け)と利用形態(直葬/一日葬/一般葬、参列人数)を切り分けて把握します。事実(所要時間、座席数、設備の有無)は公式案内(最新更新月)で裏取りし、感想は同趣旨の複数ソース一致を重視します。
事前見学と比較チェックリスト
初めての方は事前見学が効果的です。担当者同席で「受付→控室→炉前→待合→拾骨→出口」の順に歩き、段差・動線・滞留ポイントを実地で確認します。
- 駅・主要路線からの実移動時間(雨天・車椅子利用時の所要)
- 駐車台数と車寄せの位置、タクシー待機の可否
- 控室の定員・延長単価・飲食の可否と手配方法
- 多目的トイレ、授乳室、エレベーターの位置
- 友引・繁忙期の運用(受付~拾骨の平均所要)
- 骨壺・骨箱の基本セットと追加選択の単価(最新の公式表記を確認)
ケース別の選び方と比較ポイント
直葬は“移動最短・必要最小限”、一般葬は“式場併設・導線・駐車場”、高齢・遠方が多い場合は“段差とアクセス”を最優先にします。
直葬・小規模向け:移動最短と必要最低限の設備
直葬(火葬式)は移動距離の短さと控室の使い勝手が要点です。自宅や安置施設から近い火葬場を基点にし、到着→受付→火葬→拾骨がスムーズな場所を選びます。
控室の最小時間で足りるか、少人数でも落ち着ける広さかを実見学で確認します。費用面では、火葬料+控室+骨壺+安置がコアです。
任意項目(飲食や特別室)は追加効果と費用を天秤にかけ、必要かどうかで判断します。高齢の親族が多い場合、動線の短い式場併設タイプが体力負担の軽減に有利です。
一般葬向け:式場併設・会葬動線・駐車場
会葬者が一定数見込まれる一般葬では、式場併設かどうかが分かれ目になります。併設型は移動が最小化され、受付→式→出棺→火葬→拾骨の流れが一貫しやすいです。
併設でない場合は、式場―火葬場間の移動時間とマイクロバス・タクシー手配を前提に、立ち寄りやすいルートを組みます。駐車場は台数・大型可否・導線を重視します。
雨天時の集合場所や喫煙導線も混雑の起点になりやすいため、事前に掲示やアナウンス計画を用意します。会葬後の返礼・会食がある場合、控室の延長単価と飲食ルール(持込・衛生管理・ゴミ回収)を確認します。
高齢参列者や遠方家族が多い場合の配慮
移動が負担になりやすいため、段差・エレベーター・ベンチの有無、車寄せの距離、トイレ位置を優先確認します。案内板は大きな文字で、スタッフの立ち位置を入口・エレベーター前・炉前に配置すると迷いが減ります。
遠方家族には集合地点の一本化(駅改札・タクシー乗場)と時刻表リンク・所要時間の目安を事前共有します。渋滞が見込まれる時間帯は集合を15分早める、冬季は屋内待機場所の確保など、季節・時間帯リスクも織り込みます。
まとめ
口コミは条件を揃えて読み、事実は公式で裏取りします。直葬は移動最短、一般葬は導線と駐車場、高齢・遠方が多い場合は段差とアクセスを最優先にします。
評判は心強い材料ですが、人数・曜日・時間帯・形式で体験は変わります。事実(料金・設備・ルール)は最新の公式案内(更新月の明記)で確認し、見学で導線と待機ポイントを把握すると失敗が減ります。候補日は第1~第3を用意し、複数施設へ同時照会して計画を固めます。