初めてでも迷わない死亡届の書き方と訂正、提出期限と手数料も解説
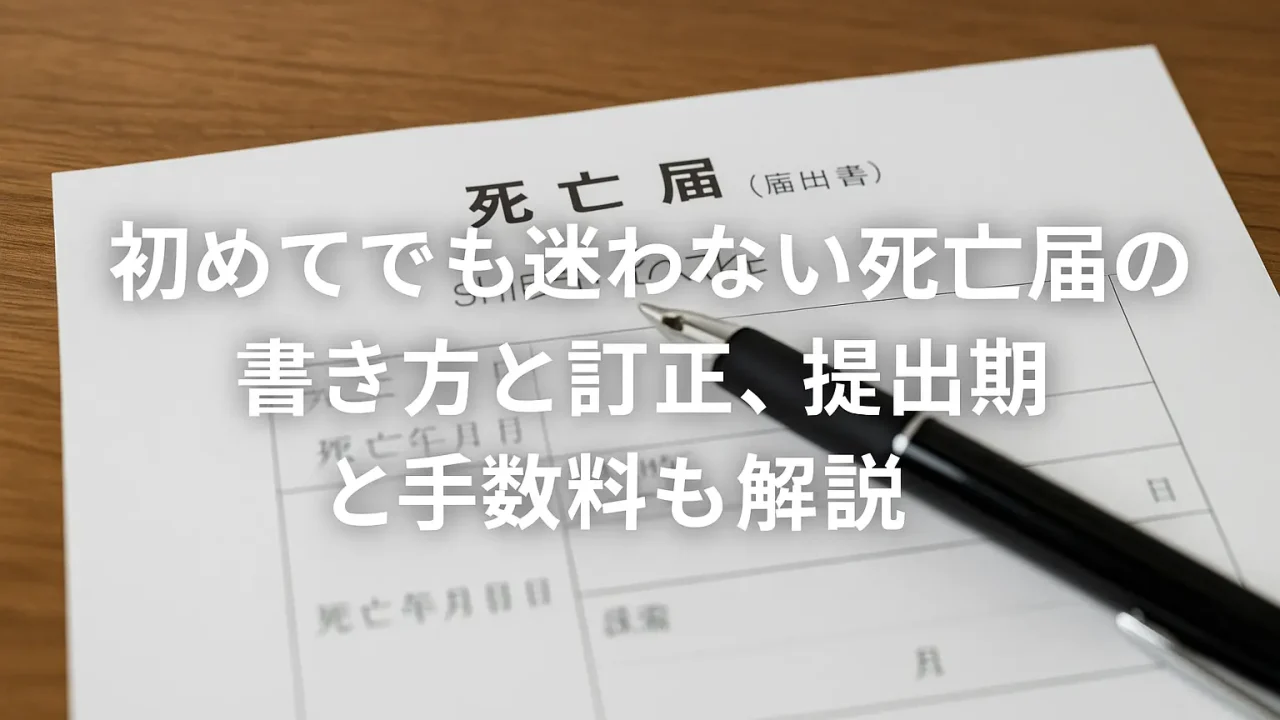
この記事では、誰がいつまでにどこへ出すのかを最初に押さえ、見本どおりの書き方と訂正のルールを解説します。本籍がわからない場合の調べ方や、時間外受付・手数料の実務も具体的に案内します。

誰が・どこへ・何を準備するか
届出人は親族等。死亡地/本籍地/届出地の役場へ7日以内に提出、誤記は窓口指示で訂正または書き直します。
届出人になれる人と実務の流れ(誰が書く)
届出人になれるのは、親族、同居者、家主・家屋管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見受任者、葬祭執行者などです(戸籍法・届書記載例の要約、2024年時点)。実務では喪主や近親者が書き、提出も行います。
手順の目安は次のとおりです。
- 医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。
- 届書の届出人欄を見本に沿って記入します。
- 役場窓口に提出し、火葬(埋葬)許可の交付を受けます。
- 誤記は窓口指示に従い、二重線・欄外記載・再作成のいずれかで対応します。
提出先の選び方(死亡地/本籍地/所在地)
提出先は「死亡地」「本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場です(戸籍法の原則、2024年時点)。急ぎの火葬予約がある場合は、火葬許可証の当日交付可否や時間外受付の有無を基準に選ぶと段取りがスムーズです。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡地 | 病院や自宅がある自治体 | 即日交付の相談がしやすい | 病院→役場→火葬場の導線が短い |
| 本籍地 | 戸籍のある自治体 | 照会が最小限 | 遠方だと移動負担が増える |
| 届出地 | 届出人の住所地 | 移動・同時手続きが容易 | 火葬場予約は別自治体になることあり |
提出前の準備チェック(見本確認・委任の可否)
提出前に次を確認します。
- 氏名・生年月日・性別・続柄・本籍・筆頭者の表記が住民票や戸籍と一致しています。
- 死亡診断書欄の転記(日時・場所・医師名)に誤りがありません。
- 連絡先・届出人署名が未記入になっていません。
- 代理提出を頼む場合は、届出人としての責任範囲と本人署名の必要性を窓口で確認します。
チェックリスト:
- 見本を参照し全欄に目を通しました。
- 本籍・筆頭者を住民票(本籍記載)や戸籍で確認済みです。
- 火葬許可の受け取り方法と予約手順を確認しました。
- 訂正方法を窓口で確認しました。
\事前相談・無料資料請求/
死亡届の書き方(見本付きの確認ポイント)
診断書欄は医師、届出人欄は届出人が記入し、住民票・戸籍に合わせて誤記・転記ミスを避けます。
医師記載欄と届出人記載欄の役割と区別
死亡診断書(死体検案書)欄は医師が記入します。届出人が手を加えると無効になるおそれがあるため、一切修正をしません。届出人欄は氏名・住所・本籍などを届出人が記入します。医師欄に疑問がある場合は、医療機関へ相談し正しい再発行や訂正の方針を確認します(医師法関連実務と自治体手引の要約、2024年)。
氏名・生年月日・本籍・筆頭者の正しい書き方
氏名は戸籍どおりの漢字・カナを記載します。旧字体・異体字の揺れは戸籍に合わせます。生年月日は西暦・和暦の指定に従い、桁や元号の誤りに注意します。
本籍は市区町村名・丁目番地まで正確に書き、筆頭者は戸籍の1行目に記載された人であって世帯主ではありません(戸籍記載の原則、2024年)。本籍が不明な場合は、本籍記載の住民票を請求して確認します(自治体公式案内、2024–2025年)。
死亡の日時・場所・原因欄の転記ミス防止
死亡日時は24時間表記の読み違いに注意します。死亡場所は病院名・住所、自宅の場合は住居表示を正確に記入します。
原因欄は医師欄の表記をそのまま転記し、略語や医学用語を勝手に言い換えないことが重要です。迷った場合は窓口で「届出人欄の書きぶり」を確認し、必要なら空欄で仮受付→後日補記の可否を相談します。
見本のチェックリスト(提出前の最終確認)
- 氏名・生年月日・本籍・筆頭者名が住民票/戸籍と一致しています。
- 診断書欄は医師記載のままで、訂正はしていません。
- 住所・連絡先・届出人署名に漏れがありません。
- 火葬(埋葬)許可の交付方法・手数料(数百円、自治体差あり/自治体告示・2024–2025年)を確認済みです。
- 万一の誤記に備え、訂正方針(二重線・欄外記載・書き直し)を窓口で確認しました。
公式見本(PDF)へのリンク
- 法務省「死亡届」記載要領・記載例(PDF案内)
- 松山市「死亡届の記載例」(PDFリンクあり)
- 東近江市「死亡届の記入例(PDF)」
- 阿波市「死亡届 記入例(PDF)」
- 群馬県板倉町「死亡届の記入例(PDF)」
本籍がわからない時の調べ方と代替手段
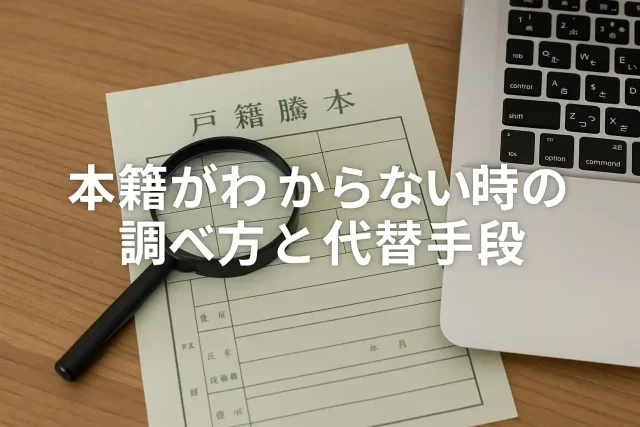
本籍は「本籍記載の住民票」か「戸籍謄本」で確認します。窓口・郵送・代理の各ルートを把握し、提出期限内に手配します。
本籍記載の住民票の取り方と必要書類
本籍が不明なら、まず「本籍・筆頭者記載の住民票」を取得します。本人または同一世帯員が市区町村窓口で請求でき、本人確認書類(運転免許証など)が必要です。手数料は概ね1通200〜400円で地域差があります。
郵送請求では、①請求書、②本人確認書類の写し、③手数料(定額小為替など)、④返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封します。到着から交付までの目安は3〜7日ですが、連休や遠隔地では1週間以上かかることがあります。住民票で筆頭者名も確認できるため、届書の筆頭者記載欄の記入ミスを防げます。
戸籍謄本の請求と代理人・郵送の手順
より確実なのは本籍地で発行される戸籍謄本(全部事項証明)です。請求者は本人・配偶者・直系親族が原則で、手数料は多くの自治体で1通450円前後です(自治体手数料の要約、2024–2025年、地域差あり)。
本籍地が遠い場合は郵送が便利で、必要書類は住民票郵送と同様に「請求書・本人確認書類の写し・定額小為替・返信用封筒」です。
代理人が請求する場合は委任状が必要です。書式は自治体サイトの様式を使い、委任者の住所・氏名・生年月日・委任事項を明記します。
郵送は配達日数+役所処理で1週間程度を見込み、葬儀日程や死亡届の提出期限(死亡を知った日から7日以内/戸籍法の要約、2024年)に間に合うよう前倒しで手配します。
親族からの確認・旧書類の手掛かり
緊急時は、親族に「過去の戸籍謄本」「不動産登記簿」「自動車の車検証」「旅券の戸籍抄本提出時の控え」など、本籍住所が写る可能性のある書類の所在を確認します。
運転免許証は原則として本籍欄非表示ですが、更新時の申請控えに手掛かりが残る場合があります。見つからないときは、住民票で当面の届書を整え、後日必要に応じ戸籍で裏取りする二段構えが現実的です。
訂正のやり方と窓口対応(ケース別)
届出人欄の誤記は二重線+訂正記載が基本、医師欄の誤りは医療機関で訂正または再作成、重大な相違は書き直します。
届出人欄の誤記:二重線・訂正記載・署名の実務
届出人が記入する氏名・住所・本籍・筆頭者などの誤記は、窓口指示に従い二重線で抹消し、欄外に正しい内容を記載します。
訂正者名の記入(署名)を求められるのが一般的で、押印は任意と案内する自治体が多いです。
数字やカナの訂正は、読み替えや追記ではなく「抹消→正記」で統一します。読みづらい場合は書き直しを求められることがあるため、清書前に見本で下書きしておくと安全です。
医師欄の誤記:医療機関への依頼と再作成の要否
死亡診断書(または死体検案書)の医師記載欄は、届出人が手を加えられません。誤りが判明した場合は、発行した医療機関に連絡し、当該欄の訂正または再作成を依頼します。
訂正は医療機関側の方法(訂正印・訂正記載等)に従います。時間外や連休をまたぐ場合、届出期限にかかることがあるため、窓口に「仮受付の可否」や「写しの持参指示」がないかを相談します。
提出後の発見・重大な相違は書き直しで対応
提出後に誤記が見つかった場合は、役場の案内に沿って訂正または再届を行います。届出人欄の軽微な誤記は窓口で訂正できることがありますが、氏名・本籍・死亡日時など重要項目の相違や、医師欄の不備は「新しい届書での書き直し」になることがあります。
火葬許可との整合も必要なため、既に予約済みの火葬日時がある場合は、許可証の再交付手続きや予約変更の可能性も含め、早急に窓口へ相談します。
\事前相談・無料資料請求/
数字でわかる手続き|期限・手数料・受付時間
期限は国内7日・海外3か月、届出は無料、火葬許可は数百円。時間外受付の可否を事前確認します。
提出期限と海外例外(7日/3か月)
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に提出します。国外で死亡した場合は「3か月以内」が目安です(戸籍法・届出期限の公式解説要約、2024年)。
休日・連休を挟むと移動や郵送で遅延しやすいため、医療機関で診断書を受領した当日から準備に入ります。
期限に遅れるおそれがあるときは、早めに提出先役場へ事情を相談し、必要書類の確認と受付可能な時間帯を押さえると安全です。火葬場の予約が先に決まる地域もあるため、届出と並行して火葬許可の交付時刻と受け取り方法も確認します。
手数料の有無:届出は無料・火葬許可は数百円
死亡届そのものの手数料は不要です。一方、火葬(埋葬)許可証の交付には多くの自治体で「数百円」の手数料がかかります。現金のみ対応の窓口や、火葬場で別途使用料が必要なケースもあります。支払い方法、領収書の名義、返金可否は自治体ごとに異なるため、事前に確認します。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡届 | 戸籍への届出 | 無料 | 提出期限は国内7日・海外3か月 |
| 火葬(埋葬)許可証 | 受理後に交付 | 数百円 | 支払い方法・交付時刻は自治体差あり |
| 火葬場使用料 | 施設利用 | 地域差大 | 予約枠と支払先が別のことあり |
受付時間と時間外窓口(24時間対応の有無)
平日の日中(例:8:30〜17:15)に戸籍窓口が開いていますが、死亡届は「宿直・時間外窓口」で休日・夜間も受付する自治体が多いです。
ただし、時間外は「預かり扱い」となり、正式な審査・処理は翌開庁日になる場合があります。火葬許可の交付や火葬場予約の可否は時間外対応が分かれるため、発行時刻・受け取り場所・予約連絡の導線をセットで確認します。
病院→役場→火葬場の動線を紙に書き出し、誰が・いつ・どこに行くかを決めておくと滞りません。
注意点とトラブル回避(事実と感想を分ける)
誤記・筆頭者・本籍の取り違えが差し戻しの主因です。一次情報の確認と訂正方針の事前合意で防ぎます。
よくある誤記(氏名カナ・筆頭者・本籍)
差し戻しの典型は、氏名の漢字・カナの揺れ、生年月日の元号・西暦誤り、筆頭者の取り違え、本籍の地番抜けです。氏名は戸籍どおりの字形で統一し、カナは住民票の表記に合わせます。
筆頭者は「戸籍の最初に記載された人」であり、世帯主とは別概念です(戸籍記載の原則要約、2024年)。本籍は市区町村名から番地まで正確に記し、わからないときは「本籍記載の住民票」または「戸籍(本籍地で発行)」で確認します。
窓口での差し戻し・再届を防ぐコツ
提出前に、届出人欄の全項目を音読しながら見本と照合します。疑義がある箇所は空欄で持参し、窓口の書式指示を受けてから記入してもかまいません。
誤記が見つかった場合は、届出人欄は二重線・欄外正記・訂正者署名が原則です。医師欄は届出人が修正できないため、医療機関に訂正または再作成を依頼します。
時間外受付に出すときは、正式交付のタイミングと火葬許可の発行可否、予約変更の必要性を同時に確認します。
一次情報の確認先(自治体告知・法令・様式)
最終判断は一次情報で行います。根拠として「戸籍法・戸籍事務手続の公的解説(2024年)」と、提出先自治体の「死亡届・火葬許可の案内ページ(2024–2025年)」、窓口で配布される「記入例(見本)PDF」を参照します。
地域により様式・運用・料金が異なるため、ネットの体験談は参考にとどめ、届出先の電話番号・受付時間・必要書類・手数料の最新情報を必ず確認します。控えとして、問い合わせ日時・担当課名・確認内容をメモに残すと、家族間の共有が円滑です。
よくある質問
基本は書き直しが確実です。自治体によって軽微な誤記は二重線+訂正印で認める場合もあるため、窓口の指示に従ってください。修正液は使えません。
本籍地の市区町村で戸籍(全部事項証明)を取得して確認します。家族の保管書類(戸籍謄本、住民票の除票など)も手掛かりになります。
期限は「死亡を知った日から7日以内」(国外は原則3か月以内)。届出自体は無料ですが、埋火葬許可証の手数料(数百円〜)と診断書の文書料がかかる場合があります。
楷書で正確に、数字は算用数字で統一します。住所や氏名の旧字体・略字、年月日の元号/西暦の混在に注意し、迷ったら見本と記入例で確認します。
戸籍の最初に記載される人のことです。死亡届には本籍と合わせて筆頭者氏名の記載欄があるため、戸籍で正確に確認して書きます。
届書左側(届出人記載欄)を正確に記入して初めて受付可能です。右側の死亡診断書(または死体検案書)は訂正できないことが多く、誤りは医療機関で再発行の指示に従います。
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。夜間・休日は当直窓口で預かり対応の自治体もあります。
署名が必須で、押印は任意の自治体が増えています。押印要否は窓口で確認します。
本人確認書類、届書、(必要に応じて)戸籍、訂正理由が確認できる資料を用意します。窓口の指示に沿って新しい届書へ転記する場合があります。
受理後に交付され、火葬・埋葬の予約に必要です。交付タイミングや手数料は自治体で異なります。
役所窓口の掲示や配布資料、自治体サイトの記入例にあります。最新の様式かを必ず確認してください。
まとめ
最短で迷わないコツは、期限・料金・受付時間を先に固め、氏名・筆頭者・本籍の一次情報で照合し、訂正ルールを把握することです。
病院で診断書を受領したら、当日中に届出先の受付時間と火葬許可の交付可否を確認します。住民票や戸籍で本籍・筆頭者を照合し、見本どおりに清書します。
誤記は届出人欄なら二重線・正記・署名、医師欄は医療機関での訂正・再作成が原則です。数字情報は自治体差と時期差があるため、提出前に公式案内で最新の手数料・時間帯・予約方法を確かめます。
\事前相談・無料資料請求/
