墓じまい・永代供養の費用相場と流れをやさしく解説
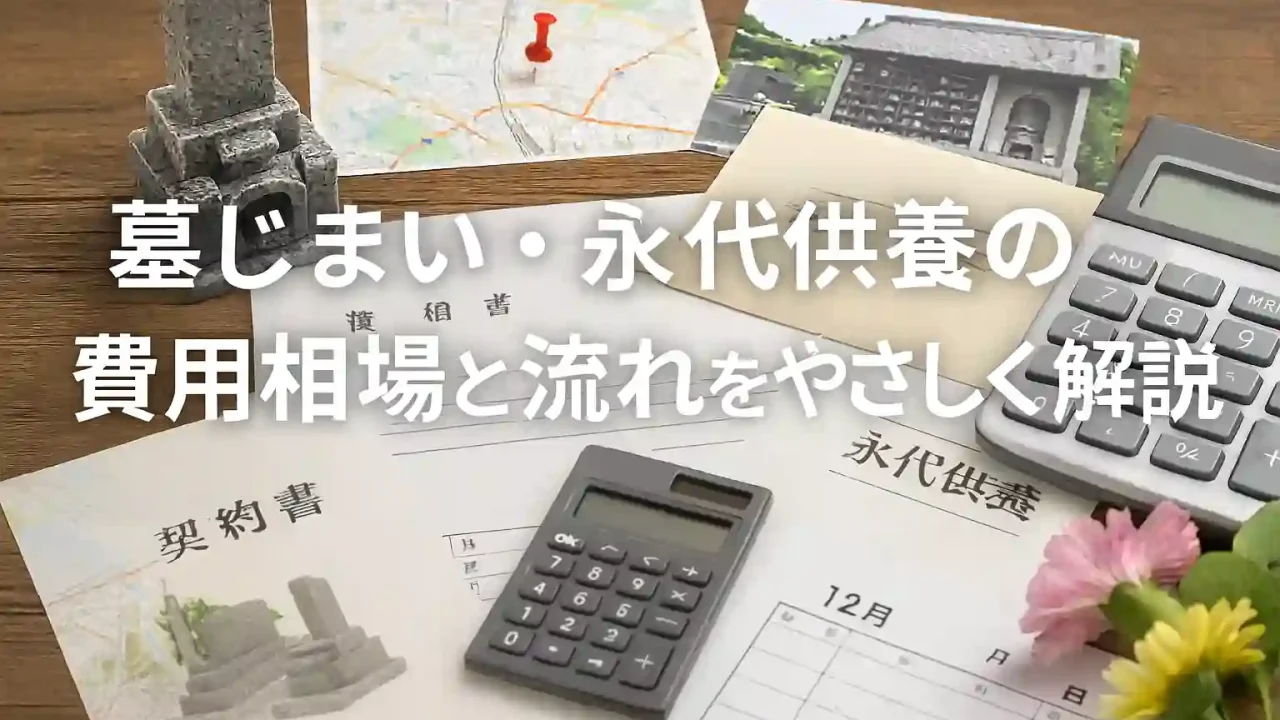
この記事では、解体撤去費・お布施・改葬手続き・受け入れ先費をわかりやすく整理し、平均的な金額感と内訳の見方、流れの全体像を解説します。はじめての方でも、見積の確認ポイントや毎年の維持費の注意点まで一気に把握できます。

最初に把握する費用の全体像と選び方
総額は「撤去費+お布施+手続き費+受入先費」の合算です。内訳と含まれる範囲を同条件・書面で比較します。
費用は合算で考える|解体・手続き・受入先
墓じまいの中心費目は、石塔・外柵・基礎の解体撤去と運搬処分、原状回復です。これに閉眼法要のお布施、改葬手続き(受入証明・埋葬証明・改葬許可)関連の実費、そして新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂・樹木葬・合祀)の費用を足し合わせて総額を見ます。
改葬の流れと書類は自治体が定め、手数料は0〜1,000円や埋葬証明300〜1,500円の案内例があります(自治体公式・2024年5月時点)。
含まれるもの/含まれないものの線引き
石材店の見積は「解体撤去一式」に見えても、基礎撤去、残土・ガラ処分、クレーン・人員増、通路養生、写真提出、原状回復(更地化・砕石厚・転圧)などの扱いが分かれます。
お布施は寺院の慣行で幅があり、閉眼のみで3〜10万円が目安、別途お車代・御膳料各5,000〜10,000円の例があるため、総額で確認します。
同条件・書面見積での比較手順
- 現地調査写真と平面図で「撤去対象(石塔/外柵/カロート/基礎)」を確定します。
- 数量根拠(㎡・m³・t)と施工条件(クレーン可否・搬出距離・車両サイズ)を明記します。
- 原状回復の仕様(更地化/砕石厚/転圧/写真提出)を文章と写真基準で固定します。
- 追加費の発生条件(雨天順延・休日・人員増)と単価を書面に残します。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 撤去・処分・原状回復 | 石塔・外柵・基礎撤去、処分、整地 | 1㎡あたり10〜15万円の解説例 | 現場条件で増減。必ず現地調査の数量根拠を確認。 |
| お布施 | 閉眼法要ほか | 3〜10万円+お車代等各5,000〜10,000円 | 菩提寺の慣習で幅。総額の意向を事前相談。 |
| 改葬手続き | 受入証明・埋葬証明・改葬許可 | 0〜1,000円/300〜1,500円等 | 役所により手数料・部数・委任状が異なる。 |
| 受入先 | 永代供養墓・納骨堂・合祀 | 5万〜100万円超まで多様 | 個別年数・銘板・維持費の有無を必ず確認。 |
\相談・見積もり無料/
永代供養の種類と費用比較(個別安置/合祀)
個別安置は参拝性が高く維持費が出やすい傾向、合祀は低価格で管理料不要が多いものの取り出し不可が一般的です。
個別安置の価格帯と確認ポイント
都内の屋内納骨堂・蔵前陵苑はベーシック85万円、ハイグレード103万円、年間護持会費15,000〜16,000円の明示があります(公式サイト・2025年9月)。
各プランに「法名授与(院号は別途お布施)」「銘板・字彫込」など含有例が示されています。低価格帯では本所廟堂が単身24万円〜/家族40万円〜の案内を掲出しています。比較時は、契約年数、銘板費、更新や護持会費の要否、免除条件の有無まで確認します。
合祀の価格帯と取り出し不可の留意点
価格を抑えたい人には合祀が選ばれます。よりそう永代供養墓は会員価格5万円(非課税)、管理費なしを明記しています(公式・2025年9月)。
一方で合祀は取り出し不可が原則です。将来の改葬予定や家族の意向に照らし、個別安置年数の有無や合同供養の頻度、証明書の発行可否を事前に確認します。
お寺・納骨堂・樹木葬の選定基準(立地・参拝・管理)
樹木葬は個別区画型と合祀型で料金差が大きく、伊東・林泉寺は「樹木葬1霊19.5万円〜」や「見守り納骨塔(合葬)7.5万円」を提示しています(公式・2025年8月)。選ぶ際は次を横並びで比較します。
- 立地・アクセス・参拝時間(屋内は天候に左右されにくいです)。
- 含まれるもの/含まれないもの(銘板・字彫・回向・証明書)。
- 毎年の維持費(護持会費・管理料)の有無と金額。
- 個別安置期間・将来の合祀条件・取り出し可否。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 屋内納骨堂(個別厨子) | 蔵前陵苑(台東区) | 85万/103万円・護持会費1.5万〜1.6万円/年 | 法名は含むが院号は別途お布施。護持会費免除条件の確認を。 |
| 屋内納骨堂(低価格帯) | 本所廟堂(墨田区) | 単身24万円〜/家族40万円〜 | 設備・契約年数・護持費の有無を確認。 |
| 合祀墓 | よりそう永代供養墓 | 会員5万円・管理費なし | 取り出し不可。合同供養や証明書の扱いを確認。 |
| 樹木葬 | 林泉寺(伊東) | 樹木葬19.5万円〜/合葬7.5万円 | 個別区画の年数・銘板費・供養方法を確認。 |
手順メモ(費用を見誤らないために)
- 受入先候補を3件選び、パンフで「含まれるもの/含まれないもの」を線引きします。
- 同条件・書面で撤去見積を2〜3社比較します。
- 役所サイトで改葬手数料と必要部数を確認し、日程を固定します。
流れと必要書類(改葬)
-e1759359607456.webp)
受入証明→埋葬(収蔵)証明→改葬許可の順で整え、法要・撤去・納骨までを日程表と書面で固定します。
受入証明・埋葬証明・改葬許可の取得手順
改葬は市区町村長の許可が必要です。まず新しい納骨先を決め、管理者から受入証明(使用承諾書等)を取得します。次に現墓地の管理者から埋葬(埋蔵・収蔵)証明を受けます。
これらを添えて現墓地所在地の役所へ改葬許可申請を行い、改葬許可証を受領します。町田市や横浜市は手数料無料の案内があり、郵送申請も可能です。受入証明が契約書の写しで代替できる等の個別運用があるため、最新の自治体ページを確認します。
閉眼法要から撤去・原状回復・納骨まで
許可証交付後、閉眼法要(読経)→出骨→解体撤去→処分→原状回復→新先での納骨の順で進めます。法要時間と工事開始時刻を事前にすり合わせ、代表者と作業責任者の連絡窓口を一本化します。
撤去後は更地化や砕石厚などの仕様どおりに仕上がっているか写真で確認し、撤去証明や管理事務所への完了届があれば受領します。改葬許可証は新先で必要になるため、原本の扱いに注意します。
家族合意とスケジュールの組み方
家族の合意形成を先に行い、①受入先確定と書類取得、②法要日程、③工事日と予備日、④納骨日を逆算で確定します。トラブルを防ぐため、次を文書化します。
- 撤去範囲(石塔/外柵/カロート/基礎)と原状回復仕様
- 写真提出の基準(ビフォー/アフターの撮影位置)
- 追加費の発生条件(雨天順延・休日・人員増)
- 支払いの時期(着手・中間・完了)と領収書の形式
料金・期間・相場の目安
費用は工事・お布施・手続き・受入先の合算で、期間は書類と日程調整を含めて数週間〜1か月強が目安です。
解体撤去・処分・原状回復の相場と注意点
撤去費は墓地の広さ・基礎の厚み・外柵の有無・搬出導線で変動します。業界調査では撤去費の目安を1㎡あたり10〜15万円が目安で、総額は31〜70万円が最多帯という実態データも公表されています。
ただし現場条件で上下するため、数量根拠(㎡・m³・t)と施工条件(クレーン可否・搬出距離)を書面で固めて比較します。最低一式の提示がある場合も、基礎撤去や処分・整地が含まれるかを確認します。
毎年の維持費(護持会費・管理料)の目安
個別安置型の納骨堂・寺院墓所では護持会費・管理料が年額で発生する例があります。都内の屋内納骨堂では年1.5万〜1.6万円の明示例があり、合祀型は管理料なしの案内が見られます。
ただし合同供養参加費や銘板更新など都度費用が発生する場合があるため、「含まれるもの/含まれないもの」をパンフレットと約款で線引きします。支払い方法(口座振替・前納)も確認します。
総額の組み立て方と追加費が出やすい項目
総額は「撤去・処分・原状回復」+「お布施」+「改葬手続き実費」+「受入先費」で算定します。お布施は閉眼のみで3〜10万円が目安で、お車代・御膳料が各5,000〜10,000円の例があります。
手続きは自治体によって改葬許可が無料〜数百円、埋葬(収蔵)証明が数百円〜1,500円程度の案内例があります。
- クレーン・人員増・長距離搬出・車両待機
- 基礎厚増し・残土・ガラの追加処分
- 通路養生・階段・狭隘地の人力搬出
- 雨天順延・休日作業・繁忙期割増
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 撤去・処分・原状回復 | 解体・搬出・処分・整地 | 1㎡あたり10〜15万円 | 現地条件で変動。数量根拠と施工条件を固定。 |
| お布施 | 閉眼法要ほか | 3〜10万円+お車代・御膳料各5,000〜10,000円 | 地域差あり。総額で住職と事前相談。 |
| 改葬手続き | 受入証明・埋葬証明・改葬許可 | 無料〜数百円、埋葬証明数百円〜1,500円 | オリジナル・部数・委任状の要否を確認。 |
| 維持費 | 護持会費・管理料 | 年1.5万〜1.6万円の明示例 | 管理料なしの合祀でも都度費用の有無を確認。 |
期間の目安(想定スケジュール)
- 受入先決定・受入証明取得:1〜2週間
- 埋葬証明取得・改葬許可申請:数日〜1週間
- 法要・工事・納骨:天候予備含め1〜2週間
全体は書類・日程調整を含めて数週間〜1か月強が目安です。
\相談・見積もり無料/
お寺とのやり取りとお布施の実務
閉眼法要の段取りと金額感を早期に共有し、書面と連絡窓口を一本化して誤解と追加費を防ぎます。
閉眼法要の相談ポイント(日時・参列・読経)
閉眼法要は撤去工事の前に行うため、寺院・石材店・家族の三者で時刻を確定します。読経の構成や所要は15〜30分が目安ですが、参列人数や焼香順で延びることがあります。
参列範囲、服装、供物、写真撮影の可否、雨天時の判断も先に決めます。移動や設営の都合があるため、石材店の集合時刻と法要終了時刻の“前後関係”を文面で残すと混乱を避けられます。記録写真は「墓前・出骨・撤去前後」の3場面で撮ると、撤去証明の裏付けとして便利です。
お布施・お車代・御膳料の目安と包み方
お布施は地域と寺院の慣行で幅がありますが、閉眼のみなら3〜10万円がよく用いられます。別途でお車代・御膳料は各5,000〜10,000円の例が多く、総額で住職に相談すると安心です。
表書きは「御布施」、お車代は「御車代」、御膳料は「御膳料」とし、白無地封筒または不祝儀袋に包みます。金額は税込/税別の観点は不要ですが、寺院側の領収書発行可否は確認します。家族で分担する場合は、代表者がまとめて授与すると失礼がありません。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| お布施 | 閉眼の読経 | 3〜10万円 | 地域差あり。総額で相談し不明点は事前確認。 |
| お車代 | 住職の交通費 | 5,000〜10,000円 | 距離やタクシー利用で変動。現地精算の可否。 |
| 御膳料 | 会食に代わる心付け | 5,000〜10,000円 | 会食の有無で判断。重複支給に注意。 |
| 封筒・表書き | 授与方法 | 御布施/御車代/御膳料 | ふくさ・袱紗を用意し崩し金を避けます。 |
離檀・規約・文書合意でトラブルを避ける
檀家を離れる場合は、寺院規約に沿って離檀届や過去帳の扱い、位牌の安置先を確認します。離檀料は一律ではなく、寺院ごとに考え方が異なります。
金額の根拠を丁寧に話し合い、合意内容は文書化します。菩提寺が管理者の墓地では、工事届や承諾書が必要なことがあるため、撤去範囲・原状回復・写真提出の基準を一枚にまとめ、寺院と石材店双方の確認印をもらうと安心です。
注意点とトラブル回避(口コミ傾向を踏まえて)
“見積の前提”と“書類の順番”でつまずきやすいため、数量根拠と手続きの段取りを先に固定します。
見積の抜け漏れ・仕様齟齬の失敗事例
よくあるのは「基礎撤去が別」「残土・ガラ処分が別」「通路養生や階段搬出が別」で、総額が後から膨らむケースです。クレーン不可や狭隘地の人力搬出、駐車場の確保費も見落としがちです。
対策は、①撤去対象(石塔/外柵/カロート/基礎)を明記、②数量根拠(㎡・m³・t)を写真付きで提示、③原状回復(更地化・砕石厚・転圧)を仕様書で固定、④雨天順延・休日作業・人員増の単価を契約書に記載、の4点です。
書類不備・日程調整・近隣対応のつまずき
「受入証明が先」「埋葬(収蔵)証明が後」「改葬許可は現墓地の自治体」という順番を誤ると再申請になり、工期が延びます。法要と工事の時間差が詰まり過ぎると、読経延長で重機待機費が発生します。
近隣には作業日時・騒音・車両出入りを掲示し、管理事務所の作業ルール(開始・終了時刻、搬出経路、清掃)を遵守します。迷ったら管理者に書面で確認し、掲示物のコピーを保管します。
契約前チェックリストと記録写真の活用
契約前に、①撤去範囲、②数量根拠、③施工条件、④原状回復、⑤追加費条件、⑥支払条件、⑦写真提出の要否を一括で確認します。
記録写真は「平面+近接」「ビフォー/アフター」「搬出経路」の3セットを最低限とし、撮影位置を図で指定すると比較が容易です。撤去証明や完了届の書式は事前に取り寄せ、受入先への提出要件(枚数・日付・撮影者名)も揃えます。
チェックリスト(コピペ用)
- 受入証明→埋葬証明→改葬許可の順番を確認します。
- 見積明細に基礎撤去・処分・養生・搬出導線を含めます。
- 追加費の発生条件(雨天・休日・人員増)と単価を書面化します。
- 法要時刻と工事開始の間に30〜60分の余裕を設けます。
- 近隣掲示・清掃・騒音配慮のルールを管理者と共有します。
よくある質問
解体撤去・お布施・改葬手続き・永代供養料の合計で数十万〜100万円前後が多いです。区画や石材量、受入先の種類で差が出ます。
受入先を先に確保し、受入証明→埋葬証明→改葬許可→閉眼→撤去→納骨の順です。書面で段取りを固定すると滞りません。
閉眼のみで3〜10万円が目安です。お車代・御膳料の要否を住職へ確認し、総額で相談して決めます。
個別型の納骨堂や寺院は護持会費・管理料がある場合があります。合祀は管理料なしが多い一方、取り出し不可が一般的です。
同条件・書面見積で比較し、不要なオプションを外します。搬出導線の確保や天候予備日設定で追加費を抑えられます。
参拝頻度や家族構成で決めます。個別は費用が上がる一方で面会性が高く、合祀は低価格で管理が軽い反面、取り出し不可です。家族合意と将来の継承可否を確認しましょう。
受入証明と埋葬証明が揃えば数日〜1週間程度で交付される例が多いです。交付部数や委任状の要否は自治体で異なるため事前に確認します。
まず意向を丁寧に説明し、閉眼日程と読経内容、お布施総額を相談します。檀家規約の離檀手続きが必要なこともあるため、文書で合意を残します。
撤去範囲(石塔・外柵・基礎)、処分量の根拠、クレーン可否、原状回復仕様、追加費の発生条件を同条件で固定し、横並び比較します。
閉眼法要→出骨→撤去→原状回復→完了確認です。代表者と作業責任者の連絡を一本化し、写真記録と撤去証明の受領を徹底します。
樹木葬は区画の広さと個別年数で差が出ます。納骨堂は立地や設備、護持会費の有無で価格帯が変化します。銘板費や更新条件も確認しましょう。
合祀や管理料不要タイプを選べば毎年の費用を抑えられます。ただし法要参加や銘板更新など、都度費用がかかるケースは契約前に要確認です。
\相談・見積もり無料/
まとめ
費目の線引きと書類の順番を可視化し、寺院・石材店・家族の合意を“文書+写真”で残すと失敗が減ります。
お布施は総額で住職と相談し、閉眼から撤去・納骨までの時間配分を余裕ある設定にします。契約書には撤去範囲・原状回復・追加費条件を明記し、改葬関連書類は役所の最新案内で確認します。近隣配慮を徹底し、完了写真と撤去証明を受入先提出用に保管します。
