市外の火葬料金はいくら?住民票以外で火葬する手続き

この記事では、市外の火葬料金と、住民票以外での手続きの要点を、搬送・安置・時間外加算まで含めて総額で比較できるよう具体例で解説します。
多くの公営・民営で可能です。ただし市民優先の運用が一般的で、市外者は料金加算や予約枠の制限があり、希望日時が取りにくい場合があります。
自治体差が大きいものの、市民が数千~1万円台でも、市外者は数万円台になる例が多いです。搬送・安置など関連費も加算され総額で差が出ます。
原則は可能ですが、受入条件や必要書類が施設ごとに異なります。火葬許可証の原本、申請者の身分確認書類、予約確認書などの提示が求められます。

要点まとめ|市外でも火葬は可能だが費用と段取りに注意
市外でも火葬は可能ですが、市民料金より高く予約も取りづらいため、許可証・予約・搬送の順で早めに固めることが大切です。
市外火葬の結論と判断基準(費用・時間・受入可否)
市外(住民票がない地域)での火葬は多くの公営・広域組合・民間施設で受け入れていますが、料金差と予約優先に明確な違いがあります。たとえば広島市は市民8,200円に対し市外59,000円と大きく差が出ます(広島市公式・使用料、2025年9月時点)。
同様に栃木県小山聖苑は管内5,000円/管外50,000円です(小山広域保健衛生組合公式、2025年4月改定)。まずは「受入可否」「市外料金」「最短予約日」を電話で確認し、取れる日程から逆算して安置・宗教者手配を調整します。
先に決める3点(火葬地/安置先/搬送手段)
- 火葬地:候補を2~3か所用意し、市外受入の有無と市外料金、最短枠を確認します。
- 安置先:自宅か安置施設かを決め、搬送距離・保管費・面会時間を比較します。
- 搬送手段:寝台車の手配と距離加算、深夜・待機・有料道路の有無を見積もります。
なお、大阪市など一部自治体では国民健康保険の葬祭費5万円が支給され、総額負担の軽減に役立ちます(大阪市公式、2024年12月公表)。
この記事の使い方
「初めてで急いで決めたい」方は、次章の“優先順位づくり”を使って火葬地を決め、並行して役所で火葬許可証を取得します。許可証は死亡届の提出先自治体が発行するのが一般的です。施設予約の電話では「市外」「希望日」「入炉人数」「持参書類」を簡潔に伝えると確定が早まります。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 広島市・市民 | 12歳以上の火葬料 | 8,200円 | 付帯設備や保管料は別。市民要件の定義あり。 |
| 広島市・市外 | 12歳以上の火葬料 | 59,000円 | 市民より高額。空き枠の取りづらさに注意。 |
| 小山聖苑・管内 | 12歳以上の火葬料 | 5,000円 | 組合管内住所の確認が必要。 |
| 小山聖苑・管外 | 12歳以上の火葬料 | 50,000円 | 2025/4改定。待合室等は別料金。 |
(出典:広島市「市営火葬場のご利用」(2025年9月掲載)、小山広域保健衛生組合「小山聖苑の使用について」(2025年4月改定)。価格は税込/税抜の明記がないため“公表額”として記載。地域・時期で変動します)
\事前相談・無料資料請求/
市外で火葬する主なケースと判断軸
「どこで火葬するか」は参列しやすさと費用のバランスで決め、死亡地・実家・納骨地の順に候補を作って可否と枠を照会します。
地元・実家・死亡地・納骨地の優先順位を決める
優先順位の作り方は、「最も多くの人が動きやすい場所」から検討します。たとえば死亡地の自治体で許可証を取得し、実家近くの火葬場で火葬、納骨は菩提寺のある地域で行う流れが現実的です。
参列者が少ない直葬であれば、空きの多い市外施設を優先し総日数を短縮する方法もあります。費用は火葬料だけでなく搬送・安置・時間外加算で差が出るため、総額で比較します(広島市や小山聖苑の公表額は市民/市外で大きく差が出ます)。
居住地と住民票の扱い(住民票以外の注意点)
火葬許可証は原則として死亡届を出した市区町村が発行します。届出地は「死亡地」「本籍地」「届出人の住所地」などが選べます。
住民票が市外でも火葬は可能ですが、各施設が定める「市民(管内)」「その他(市外)」の定義に合致しているかの確認が必要です。広島市の条例では「市民」か「その他」かで使用料と控室等の付帯料金が異なります(広島市例規集、参照条文)。
宗教者・参列者の動線とアクセスで比較する
- 候補施設2~3か所へ同時照会し、市外受入・料金・最短枠を聞きます。
- 許可証の原本持参や身分確認の要否、精算方法(現金/カード)を確認します。
- 参列者の集合場所・時間を先に決め、搬送と宗教者の入り時間を合わせます。
また、自治体の葬祭費(例:大阪市国保5万円)が支給対象なら、受給要件と申請期限もスケジュールに組み込みます(大阪市公式、2024年12月)。
料金・期間・相場|市内と市外の実額比較
市外でも火葬は可能ですが、市民(管内)より料金は高く、予約優先や受付期間に差が出るため、総額と日程で比較することが重要です。
市民料金と市外者料金の目安(差の出方と理由)
市外者料金は自治体ごとの条例や広域組合の規定で大きく異なります。たとえば広島市は「12歳以上・市民8,200円/その他(市外)59,000円」と、市外で大きく上がります(2025年9月時点の市公式)。
小山聖苑(栃木県の広域施設)も「管内5,000円/管外50,000円」で、市外(管外)は一桁高い設定です(2025年4月改定の組合公式)。これは地元住民の負担軽減や施設整備費を反映した市民優遇・管内優遇の設計によるものです。
関連費の増減:搬送・安置・待機・時間外加算
火葬料だけでなく、寝台車の距離加算、夜間待機、有料道路、安置料、控室使用料などで総額が変わります。小山聖苑では待合室や式場の料金区分が明示され、管外は一部使用料が割高です(2025年4月改定)。
市区町村の国保や後期高齢者医療の「葬祭費」(例:大阪市は5万円)を受けられる場合、総負担の抑制に役立ちます。受給要件や申請期限(時効2年)も合わせて確認します。
予約待ち期間の目安と混雑期の傾向
都市部では市民優先の運用があり、予約解放のタイミング自体が「市民先行・市外後行」と分かれる例があります。横浜市は「火葬のみの予約で、市民は10日前から・市外は3日前から」と差を設け、市民の確保を優先しています(2025年8月時点の市公式)。こうした運用は混雑期に市外枠が取りにくくなる要因です。候補施設を複数持ち、同時照会で最短枠を確保するのが現実的です。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 広島市(市民) | 12歳以上火葬料 | 8,200円 | 保管料や小動物焼却等は別区分。定義「市民」を要確認。 |
| 広島市(市外) | 12歳以上火葬料 | 59,000円 | 市民と大差。混雑時は枠確保に時間。 |
| 小山聖苑(管内) | 12歳以上火葬料 | 5,000円 | 霊安室・待合室等は別料金。 |
| 小山聖苑(管外) | 12歳以上火葬料 | 50,000円 | 令和7年4月改定。付帯施設の一部も管外は割高。 |
| 横浜市(予約運用) | 予約解放差 | 市民10日前/市外3日前 | 市民先行で市外は直前枠のみ。曜日・時間で変動。 |
(出典:各自治体・組合公式/広島市2025年9月掲載、小山広域保健衛生組合2025年4月改定、横浜市2025年8月。価格は公表額で税込/税別の明記がない場合は“公表額”として記載、地域・時期で変動します)
手続きと必要書類|同一都道府県で市外火葬する流れ
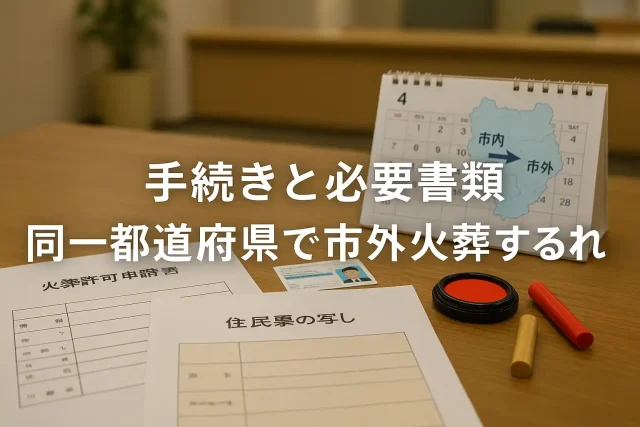
死亡届の提出→火葬許可証の取得→市外施設の予約の順が基本で、許可証原本を当日持参します。届出地と火葬地が異なっても原則手続きは可能です。
死亡届・火葬許可証の取得先と提出先(市外ケース)
火葬許可証は、市区町村役所で死亡届と同時に交付されるのが一般的です。届出先は「死亡地」「本籍地」「届出人の住所地」のいずれかで、届出地と火葬地が異なっても問題ありません。
新宿区は死亡届の受付後に「死体火葬許可証」を交付する旨を明示しています。多くの自治体で夜間・休日も死亡届の受付自体は可能ですが、許可証の実交付は開庁時間内に限る場合があります。
予約方法・持参書類・当日の受付手順
予約は葬儀社が代行する場合が多いものの、遺族が直接行う施設もあります。八王子市では、他市で死亡届を出した場合でも「他市区町村発行の埋火葬許可証」を持参すれば火葬室の使用申請が可能で、市外住民は所定の使用料が必要と案内しています。
当日は原本の許可証、申請者の身分確認書類、予約確認の控えを持参します。
- 受付で埋火葬許可証(原本)と予約情報を提示します。
- 棺の受け入れ・入炉時刻・収骨方法の説明を受けます。
- 精算(現金/カードの可否は事前確認)を行い、火葬執行済みの押印を受けます。
- 返却された許可証は、納骨手続き(埋葬許可扱い)に使用します。
(許可証の扱い・同一書式の兼用は自治体運用により異なるため、事前確認が安全です)
委任状・身分確認・原本管理のポイント
届出人=申請者が基本ですが、実務上は葬儀社が代理提出・受領することが一般的で、委任状を求められる場合があります。許可証原本は再発行に手数料がかかる自治体があるため、紛失防止が必須です。
また、火葬は「死亡から24時間経過後」が原則で、時間短縮ができない点も踏まえ日程を組みます。
\事前相談・無料資料請求/
県外で亡くなった/県外で火葬する場合の進め方
届出地と火葬地が別でも実施できます。死亡届→火葬許可証→火葬場予約→搬送・安置の順で、原本管理と日程確保を最優先に進めます。
死亡地の届出→火葬許可証取得→火葬地へ搬送
死亡届は「死亡地/本籍地/届出人の住所地」のいずれかで提出でき、受理後に火葬許可証(埋火葬許可証)が交付されます。県外で火葬する場合も、交付された許可証原本を火葬地施設に提出すれば手続きできます。
当日の流れは、受付で許可証原本の確認→入炉時刻・収骨方法の説明→精算→許可証への押印返却です。返却後の許可証は納骨時に使用するため、折れや紛失を避けて保管します。
なお、火葬は原則として死亡後24時間を経過してから可能です。これは「墓地、埋葬等に関する法律」第3条に基づく全国共通の基準です(厚生労働省掲載法令、2025年)。
長距離搬送と安置先確保(費用・時間の見積もり)
県外搬送では、寝台車の距離加算・深夜割増・有料道路・待機料金が乗ります。安置は自宅か安置施設かで費用が異なり、霊安室利用や待合室・式場使用料が別途かかるケースもあります。例えば栃木県の小山聖苑は管内と管外で火葬料だけでなく付帯施設の使用料区分も明示しています。
費用の一部は公的給付で軽減可能です。大阪市の国民健康保険・後期高齢者医療では葬祭費5万円が支給され、申請期限は原則2年です。
混雑都市では市民優先の予約運用があり、県外(市外)枠は直前開放の例があります。横浜市は「市民10日前/市外3日前」からの予約開始と明記しています。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 火葬料(管内) | 12歳以上 | 例:5,000円 | 組合・市の定義に合致が必要。 |
| 火葬料(管外) | 12歳以上 | 例:50,000円 | 令和7年4月改定などの期日に注意。 |
| 市民/市外差 | 12歳以上 | 例:8,200円/59,000円 | 広島市の公表額。地域差あり。 |
| 付帯施設 | 待合室・霊安室等 | 施設により別料金 | 区分・時間帯で変動。 |
| 公的給付 | 葬祭費 | 5万円 | 申請期限2年、要領収書。 |
納骨地が別のときの書類確認と日程調整
火葬後、許可証に「火葬執行」の記載・押印が入り、納骨時の必要書類として扱われます。納骨先の規則(菩提寺・納骨堂・霊園)で予約や許可証類の提示方法が違うため、県外の移動時間と合わせて先に日程を押さえます。宗教者の都合・参列者の合流地点・交通事情も踏まえ、火葬日時→納骨日時の順に確定すると調整が楽です。
- 火葬場は2~3施設に同時照会(受入可否・市外料金・予約開始日を確認)。
- 安置先は面会可否と保管費を確認。長距離搬送なら到着時刻に合わせて鍵・担当者の立会いを設定。
- 許可証原本は防水ファイルで携行し、写しを家族で共有。
注意点と口コミの傾向
トラブルの多くは「予約が取れない」「書類不備」「時間外加算」の3点です。市外枠の運用と必要書類、精算方法を事前確認すれば回避しやすくなります。
よくあるトラブル
予約不可:大都市は市民先行のため、県外(市外)枠は直前開放が多く、希望日時を押さえにくい傾向です(横浜市の先行受付例、2025年8月)。
書類不備:他市区町村発行の埋火葬許可証の原本持参が必要です。八王子市は「他市発行の許可証を持参」と明記しています(2025年9月)。
時間外加算:夜間到着・早朝入炉などで待機費や時間外料金がかかる場合があります。付帯施設料や霊安室料の区分は事前に確認します。
法律上の待機:死亡後24時間未満は原則火葬できず、やむを得ない例外を除き日程短縮は困難です(法令、2025年)。
利用者の声:高評価ポイントと不満点
公式発表にもとづく制度と運用:市民・管内優遇の料金設定、予約先行は条例・運用で明記されています。
口コミ:良い点…市外でも受入があれば日程短縮につながる、直葬で移動負担が減った。不満点…市外料金が高い、直近まで予約が開かず段取りが組みづらい、付帯施設が割高。※感想は一般的傾向の整理であり、各施設の実際の対応は最新の公式情報を要確認とします。
失敗を防ぐチェックリスト(予約前・当日・精算時)
- 候補2~3施設に同時照会(市外受入/予約開始日/必要書類)。
- 搬送距離・到着時刻・安置先の鍵・立会いを確定。
- 公的給付(葬祭費5万円など)の要件・期限(時効2年)を確認。
- 当日は埋火葬許可証の原本、身分確認書類、予約控えを携行。
- 入炉時刻・収骨人数・精算方法(現金/カード)を再確認。
- 押印済み許可証を受け取り、納骨先と日程を確定。
よくある質問
死亡地の市区町村で死亡届→火葬許可証を取得→火葬地の施設へ予約・提出が基本です。納骨地が別なら埋葬許可の扱いも併せて確認します。
実務上は葬儀社が代行するのが一般的ですが、直葬などでは遺族が直接予約する施設もあります。いずれも許可証や身分証の準備が必要です。
火葬許可証(原本)、申請者の身分確認書類、予約確認書(施設指定書式があれば)、故人情報が分かる書類が基本です。搬送を伴う場合は搬送同意書や委任状を求められることがあります。
施設の混雑と運用次第です。市民優先の火葬場では市外枠が限られ、希望日の取得が難しい場合があります。希望日が固定なら複数施設へ同時照会が有効です。
死亡地で死亡届を出し火葬許可証を取得したうえで、実家近くの火葬場を予約します。搬送距離により費用と時間が増えるため、安置先と搬送手段を先に確保しましょう。
一般に公営は市民優遇で市外者加算が大きく、民営は一律設定のことがあります。ただし付帯設備や時間帯による加算があるため総額で比較することが重要です。
可能です。直葬は式を省略するためスケジュールは組みやすい一方、許可証の取得・搬送・安置の段取りを遺族側が早めに整える必要があります。
火葬は市外でも、納骨は墓地・納骨堂の管理規則に従います。埋葬許可(火葬済証の裏書等)を確認し、納骨先の受入条件と日程を事前に調整してください。
距離課金が一般的で、深夜・待機・有料道路等の加算が発生します。複数社から同条件で見積りを取り、往復有無やストレッチャー料金の含まれ方を確認しましょう。
あります。感染症対応や運用上の制限、改修期間などで受入を止める場合があります。候補を複数用意し、最新の受入条件・必要書類を事前確認してください。
まとめ
県外火葬は「法令上の24時間」「市外枠の予約運用」「許可証原本」の3点管理が成否を分けます。候補の複線化と書類の先回りが最短化の近道です。
県外でも火葬は可能です。まず死亡届と火葬許可証を確実に取得し、受入可否・予約開始日・市外料金を同時に確認します。
搬送・安置・付帯施設まで総額で見積もり、公的給付の活用も検討します。許可証原本は納骨まで一貫管理し、押印後の返却を必ず受けます。最新の料金・運用は自治体・施設の公式情報で更新されるため、最終決定前に再確認します。
\事前相談・無料資料請求/
