お悔やみの言葉をLINEで送るには?友達・同僚・上司別の例文集

突然の訃報を受けたとき、すぐに連絡できる手段としてLINEを利用する方も増えています。しかし「失礼にならない言葉選びが分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、友達・同僚・上司といった立場ごとにふさわしいお悔やみの言葉を例文で紹介し、送るタイミングや注意点もわかりやすく解説します。

お悔やみの言葉をLINEで伝えるときの基本ポイント
近年は連絡手段としてLINEが広く使われており、訃報を知った際に「お悔やみの言葉」をLINEで送るケースも増えています。しかし、便利さの一方で、対面や電話で伝える場合と比べて注意すべき点があります。
ここでは、メールや電話との違い、使ってはいけない表現、そして送る際に心がけたいポイントを整理します。
メールや電話との違いとLINEを使う際の注意点
まず、LINEはメールよりも即時性が高く、相手がすぐに読む可能性があるため、タイミングに細心の注意を払う必要があります。特に葬儀中や準備の最中に通知が届くと、かえって迷惑になることもあります。
そのため、訃報を知った直後に送るのではなく、落ち着いたタイミングを見計らうことが大切です。
また、電話と違って声の抑揚や温度感が伝わらないため、文章表現に慎重さが求められます。絵文字やスタンプは弔事にはふさわしくないため、使用は避けるべきです。LINEは気軽なツールですが、送信前に「これはビジネスメールのように丁寧か」を確認することを心がけましょう。
避けるべき表現やマナー違反になりやすい言葉
お悔やみの言葉では「重ね重ね」「再び」といった繰り返しを連想させる言葉は避けるのが一般的なマナーです。
例えば「ご冥福をお祈りします」は広く使われますが、浄土真宗では「冥福」という考えがないため「安らかなご往生をお祈りいたします」と表現を変える必要があります。このように、宗教的な背景にも配慮できると丁寧です。
さらに、「がんばって」「元気を出して」といった励ましの言葉は、相手の悲しみに寄り添えていない印象を与える場合があります。基本は、短く簡潔に、相手の悲しみを受け止める言葉を選ぶことです。
- 「このたびはご愁傷さまでございます」
- 「突然のことで言葉もございません」
- 「心よりお悔やみ申し上げます」
このような定型的な言い回しを選べば、失礼にあたることはほとんどありません。
相手の心情に配慮したシンプルで短い言葉が大切
LINEで送るメッセージは、長文にならないよう注意しましょう。相手は葬儀準備や弔問対応で非常に忙しく、長い文章を読む余裕がないことが多いからです。実際、「簡潔に心情が伝わる文がありがたかった」と話す遺族も少なくありません。
例えば友人に送る場合は「お知らせいただき驚いています。心よりお悔やみ申し上げます。」といった短文で十分です。同僚や上司に送る場合も、「ご尊父様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。」など、形式的ながら丁寧な言葉を選ぶのが良いでしょう。
加えて、参列できない場合には「本来であれば直接お伺いすべきところ、LINEで失礼いたします」と一言添えると、礼を欠いた印象を和らげられます。短さの中に思いやりを込めることが、LINEでのお悔やみを伝える際の最大のポイントです。
\無料の資料請求は下記から/
友達に送るお悔やみLINEの例文
親しい友人に向けて「お悔やみの言葉」をLINEで伝える場合は、形式的すぎるとよそよそしく感じられる一方、砕けすぎても失礼になることがあります。ここでは、訃報を知った直後、葬儀に参列できない場合、そして親しい関係だからこそ伝えられる言葉の例を紹介します。
突然の訃報を聞いたときに送る言葉
友達の家族や身近な人の訃報を聞いたときは、まず驚きと悲しみを共有するシンプルなメッセージが適しています。LINEは即時性があるため、長々とした文章よりも、気持ちを率直に表す短文が望ましいでしょう。
- 「知らせを聞いて驚いています。心からご冥福をお祈りします。」
- 「突然のことで、まだ信じられません。どうか無理をしないでください。」
- 「大切なご家族を亡くされたこと、言葉も見つかりません。心よりお悔やみ申し上げます。」
このように、感情を素直に表現しつつ、相手の気持ちに寄り添う姿勢を示すことが大切です。
参列できない場合に送るお悔やみメッセージ
事情により葬儀に参列できない場合は、その点をきちんと伝えたうえで、相手への思いやりを表現することが必要です。単に「行けない」と伝えるのではなく、丁寧な断りと配慮を加えることで誠意が伝わります。
- 「本来ならお伺いすべきところですが、都合により参列できず申し訳ありません。心よりご冥福をお祈りいたします。」
- 「遠方にいるため直接お悔やみをお伝えできませんが、心はご家族と共にあります。」
- 「LINEでのご連絡になり失礼いたします。お別れに伺えませんが、深く哀悼の意を表します。」
このような表現を使えば、参列できないこと自体はマイナスにならず、むしろ誠実さを感じてもらえるでしょう。
親しい友人だからこそ使える柔らかい表現
長年付き合いのある親友や特に近しい友人の場合、形式張った言葉よりも、気持ちを込めた柔らかい表現が適していることもあります。ただし、あくまで弔事であることを忘れず、節度を守ることが大切です。
- 「本当に大変だったね。つらい気持ち、少しでも分かち合えたらと思っています。」
- 「いつでも話を聞くから、一人で抱え込まないでね。」
- 「あなたの気持ちが少しでも軽くなるよう祈っています。無理しないで。」
このようなメッセージは、親しいからこそ相手の心に寄り添うことができる表現です。ただし距離感を誤ると相手の負担になるため、状況を見極めることが重要です。
友達へのお悔やみLINEは「丁寧さ」と「親しみ」のバランスを取ることが鍵になります。相手との関係性を考慮しながら、心を込めた一文を送るようにしましょう。
同僚や仕事関係の人に送るお悔やみLINEの例文
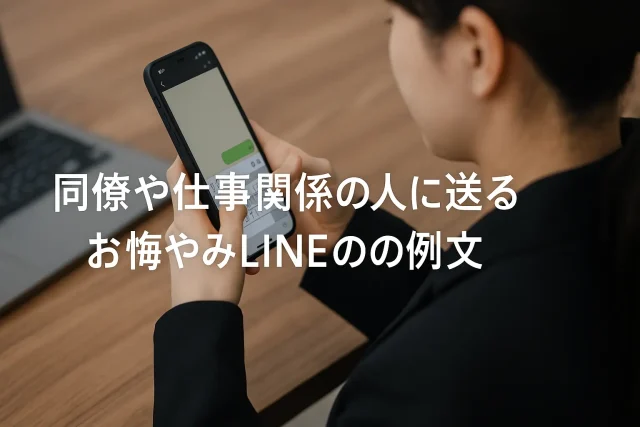
同僚や仕事関係の人に対してお悔やみの言葉をLINEで送る場合は、友達のときよりも一層フォーマルさが求められます。仕事上のつながりがあるからこそ、社会人としてのマナーを意識しながら、相手に寄り添う気持ちを伝えることが大切です。ここでは、社内の同僚、取引先や仕事仲間、そして「お悔やみ申し上げます」の使い方について解説します。
社内の同僚に送る場合の注意点と例文
同じ会社の同僚が身内を亡くされたときには、関係性が近くても言葉選びには注意が必要です。普段はフランクな会話をしていても、訃報に対しては簡潔かつ丁寧な表現を選ぶのが基本です。絵文字や顔文字は避け、文末は「です・ます」で統一することで失礼になりません。
- 「このたびはご愁傷さまでございます。大変な中で無理をなさらないようにしてください。」
- 「突然のことでお辛いことと存じます。少しでも気持ちが休まりますようにお祈りいたします。」
- 「心よりお悔やみ申し上げます。どうか体調を崩されませんようご自愛ください。」
同僚だからこそ、気遣いの言葉を一言添えると相手に安心感を与えることができます。
取引先や仕事仲間に送る場合の例文
仕事上のパートナーや取引先の担当者が喪に服している場合は、特に礼儀正しい表現が必要です。直接会う前にLINEで連絡する場合でも、ビジネスメールに近いフォーマルさを意識すると良いでしょう。余計な説明や日常的な話題は避け、必要最小限の丁寧な文面にとどめます。
- 「ご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。」
- 「突然のことで驚いております。心よりご冥福をお祈りいたします。」
- 「このたびのご不幸に際し、心からお悔やみ申し上げます。ご遺族の皆様のご心痛はいかばかりかと拝察いたします。」
こうした文章は、形式的でありながら相手に誠実さを伝える効果があります。ビジネスの関係性を損なわず、相手を思いやる姿勢を示せるでしょう。
「お悔やみ申し上げます」を正しく使う方法
「お悔やみ申し上げます」という言葉は、弔事におけるもっとも一般的で無難な表現です。誤って「お悔やみいたします」と略す方もいますが、敬語としては「申し上げます」と結ぶ方が適切です。特に仕事関係では正しい言い回しを使うことで、常識ある印象を与えられます。
また、文章の冒頭や末尾に添えると自然にまとまります。例えば「突然の訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。」や「心からお悔やみ申し上げます。どうかご自愛ください。」のように配置すると、形式と気持ちの両立が可能です。
同僚や仕事仲間へのお悔やみLINEは、相手の立場に敬意を払いながら、簡潔に伝えることが最大のポイントです。過不足なく思いを込めることで、社会人としての信頼も守ることができるでしょう。
\無料の資料請求は下記から/
上司や目上の方に送るお悔やみLINEの例文
上司や目上の方に対してお悔やみの言葉をLINEで送る場合は、友人や同僚以上に慎重な対応が求められます。立場のある方に対しては、敬語を適切に使うとともに、ビジネスシーンにふさわしい配慮が必要です。
ここでは敬語を使った例文や注意点、そしてLINE以外の連絡手段を検討すべき場合について解説します。
敬語を用いた丁寧な例文
目上の方に向けては、口語的な表現を避け、格式を重んじた言葉を選びましょう。特に「ご逝去(せいきょ)」や「ご尊父様」「ご母堂様」といった尊敬を表す表現を使うと、失礼のない文面になります。
- 「ご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。」
- 「ご母堂様のご訃報に接し、心からお悔やみ申し上げます。ご遺族の皆様のお気持ちをお察しいたします。」
- 「突然のことでさぞご無念かと存じます。ご冥福をお祈り申し上げます。」
このような例文は、定型的ではありますが、社会人としての常識と誠意を伝えるには十分です。
不躾にならないための注意点
上司や目上の方に対しては、短すぎる文面や軽い口調は避けるべきです。例えば「びっくりしました」「大変ですね」といった表現は、不躾な印象を与えかねません。また、友人向けには許される「元気を出してください」といった励ましの言葉も、目上の方には控えたほうが無難です。
さらに、LINEのカジュアルさをそのままに出してしまうと失礼になるため、句読点の位置や敬語の使い方にも注意を払いましょう。「書き言葉としての丁寧さ」を意識することが、誠意を示す上で大切です。
LINEではなく電話・メールに切り替えるべきケース
場合によっては、LINEでの連絡が不適切となることもあります。特に直属の上司や会社の経営層など、立場のある方に関しては、LINEでは軽すぎる印象を与えることがあります。その際は電話やビジネスメールを選ぶほうが安心です。
例えば次のようなケースでは、LINE以外の手段が望ましいと考えられます。
- 社内規則や慣習として弔事は電話・メールで伝えることが一般的な場合
- 普段から業務連絡をメールで行っており、LINEを使わない関係性の場合
- 会社を代表して連絡する立場にある場合
どうしてもLINEで送る場合は、「LINEでのご連絡にて失礼いたします」と前置きを加えると、軽率な印象を和らげることができます。
上司や目上の方へのお悔やみLINEは、言葉遣いと配慮のバランスが求められます。相手との関係性や状況をよく考え、最適な方法を選ぶことが、失礼を避ける最大のポイントです。
お悔やみLINEとお悔やみメールの違いと使い分け
「お悔やみの言葉」を送る手段としては、LINEとメールのどちらを選ぶべきか迷う方も少なくありません。どちらも文章で伝える点は共通していますが、利用シーンや相手との関係性によって適切な使い分けが必要です。
ここでは、LINEが適している場合、メールを選ぶべき場合、そして両方を併用する際の考え方を解説します。
LINEで送るほうが適している場合
LINEは即時性が高く、普段から親しい間柄で利用している場合には有効な手段です。特に友人や同僚など、日常的にLINEでやりとりをしている相手であれば、違和感なく気持ちを伝えられます。
- 訃報を聞いてすぐに気持ちを伝えたい場合
- 相手が普段からLINEを主な連絡手段としている場合
- 形式よりも迅速さや親しみを優先したい場合
ただし、LINEはカジュアルな印象が強いため、送信時には「LINEでのご連絡で失礼いたします」と前置きを加えると丁寧です。
メールで送った方がよい場合
メールはLINEに比べてフォーマルな印象を与えられるため、仕事関係や目上の方に対して適しています。また、文章を落ち着いて構成できるため、形式を重んじたい場合に適した手段です。
- 上司や取引先など、ビジネス関係の相手に送る場合
- 相手がLINEを使っていない、または業務連絡で使用しない場合
- 記録として残したい、文面をきちんと整えて伝えたい場合
特に企業文化や地域の慣習によっては「LINEでの弔事連絡は不適切」とされることもあるため、迷ったらメールを選んだほうが無難です。
両方を使い分ける際の考え方
状況によっては、LINEとメールを併用するのが望ましい場合もあります。例えば、まずはLINEで簡潔にお悔やみを伝え、その後に改めてメールで丁寧な文面を送る方法です。これにより、即時性とフォーマルさの両方を兼ね備えることができます。
実際の例としては以下の流れが考えられます。
- 訃報を受けてすぐにLINEで「突然のことで驚いています。心よりお悔やみ申し上げます」と送る
- 落ち着いたタイミングで、メールにて正式な文章で再度お悔やみを伝える
このように二段構えで伝えることで、迅速さと礼儀の両立が可能になります。重要なのは、相手がどの手段を心地よく受け止められるかを想像することです。相手との関係性や状況を踏まえ、最適な方法を選びましょう。
お悔やみLINEを送るタイミングと返信の仕方
お悔やみの言葉は内容だけでなく、送るタイミングや返信の方法によっても相手への印象が大きく変わります。特にLINEは通知がすぐに届くため、相手が忙しい最中に受け取ることになる可能性もあり、配慮が欠かせません。
ここでは、送信のタイミングや返信への対応について具体的に解説します。
連絡を受けた直後に送るべきかの判断
訃報を聞いたとき、多くの人はすぐに連絡した方がよいか迷います。基本的には「できるだけ早く」が望ましいですが、相手が慌ただしい状況にある可能性を考慮し、長文や詳細な質問は控えましょう。
- 訃報を知らせる連絡を受けた直後に、短いお悔やみの言葉を送る
- 「ご連絡ありがとうございます。心よりお悔やみ申し上げます。」と簡潔に伝える
- 詳細を聞きたい場合は、落ち着いた頃に改めて伺う
特に葬儀の日程や場所については、相手が知らせていない段階で質問すると負担をかけてしまうため注意が必要です。
葬儀後に送る場合の注意点
葬儀の最中や直後は、遺族が非常に忙しく精神的にも疲弊しています。そのため、あえて数日置いてからお悔やみLINEを送るのも一つの方法です。遅れて送る場合には、「ご葬儀が無事に終えられたことと存じます」といった前置きを入れると、失礼のない印象を与えられます。
- 「ご葬儀を終えられたばかりのところ、遅れてのご連絡で申し訳ございません。心よりお悔やみ申し上げます。」
- 「大変な中でのご対応、お疲れのことと存じます。どうかご無理なさらずお過ごしください。」
タイミングが遅れても、誠意のある一文を添えることで、気持ちはしっかり伝わります。
返信を受けたときの適切な対応例
お悔やみLINEに対して相手から返信が届いた場合は、長々と返す必要はありません。遺族は多数の連絡に対応している可能性があるため、負担を増やさないことが大切です。返信には感謝を示す短い言葉で十分です。
- 「ご丁寧にありがとうございます。どうかご自愛ください。」
- 「お返事をいただき恐縮です。お体を大切にお過ごしください。」
また、返信がなくても心配する必要はありません。遺族は精神的にも体力的にも余裕がないことが多いため、返事を求めない姿勢が望ましいです。送る側の役割はあくまで「気持ちを伝えること」であり、返事を期待するものではないと考えると良いでしょう。
このように、タイミングと返信への配慮を意識することで、相手に余計な負担をかけず、真心を伝えることができます。
\無料の資料請求は下記から/
まとめ:相手を思いやる気持ちを第一にお悔やみの言葉を伝えよう
お悔やみの言葉をLINEで送るときに最も大切なのは、形式的な文面の整え方以上に「相手の心情に寄り添う気持ち」です。LINEは身近で便利なツールですが、同時に弔事の場面では軽さが出やすいため、表現や送信のタイミングに十分な注意が必要です。
本文で解説したように、友人にはシンプルで率直な言葉を、同僚や仕事関係にはフォーマルな言い回しを、上司や目上の方には敬語を重んじた表現を選ぶことが重要です。また、宗教的な背景によって使うべき表現が異なる場合もあるため、「ご冥福」「ご往生」などの言葉を適切に使い分けることが求められます。
さらに、送るタイミングも配慮が必要です。訃報直後に送る場合は簡潔に、葬儀後に送る場合は「遅れて申し訳ない」という気持ちを添えると良いでしょう。返信に対しては過度な負担をかけず、短い感謝の言葉で十分です。
例文を参考にしながら、自分の言葉で気持ちを表現することも大切です。例えば、「心よりお悔やみ申し上げます」といった定型文に、自分なりの気遣いを一文添えることで、相手に誠意が伝わりやすくなります。
LINEという簡便な手段であっても、そこに込める思い次第で、相手にとって大きな支えとなるでしょう。
最後に覚えておきたいのは、お悔やみの言葉は「完璧に正しい文章」を目指すよりも、「心を込めて伝える」ことが何よりも大切だという点です。形式にとらわれすぎず、相手の状況に寄り添った一言を届けることこそが、真のマナーといえるでしょう。