死亡届を出す前に:銀行への連絡順と口座の扱い
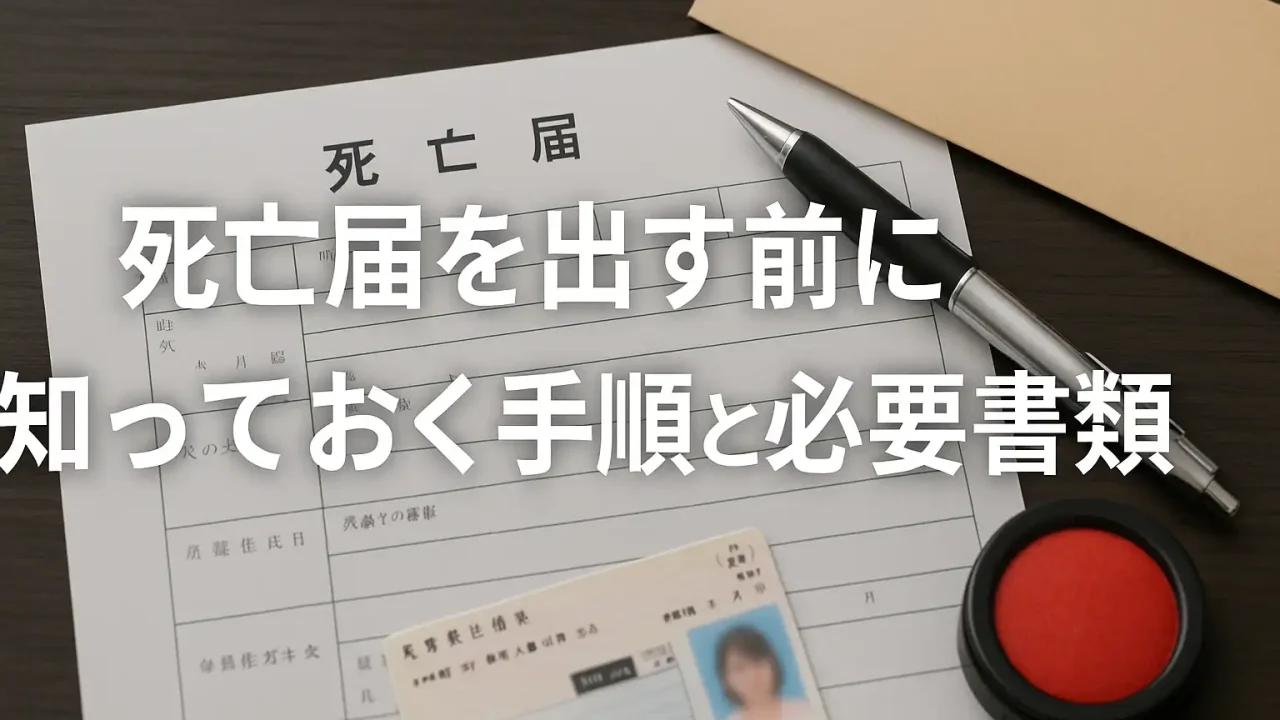
死亡届を出す前に押さえるべきは、連絡の順番と“触ってはいけない口座”。本記事では、連絡先の選び方、凍結後の正規の払戻し、必要書類まで、迷わない初動をコンパクトに整理します。

最初に要点|届出前の優先順位と最初に行うこと
最優先は連絡と書類確保です。医療機関・親族・葬儀社へ順に連絡し、死亡診断書と本人確認類を整え、金融・年金は停止連絡を先に入れます。
連絡の優先順位(医療機関・親族・葬儀社)
はじめに医療機関から死亡診断書(または死体検案書)を受け取ります。次に近親者へ連絡し、葬儀社の搬送手配と安置先の確保を行います。ここまでが「当日中の初動」です。葬儀の日取りは火葬場の空き次第で決まるため、連絡担当者を1名指名し、連絡のハブにします。
初動チェック:
- 医療機関から診断書を受領した。
- 近親者・関係者へ一斉連絡を済ませた。
- 葬儀社と搬送・安置先を確保した。
口座・カード・年金の連絡順と停止方針(原則のみ)
銀行口座・クレジットカード・年金等は「利用停止」の連絡を速やかに行います。死亡後のATM引き出しや決済の継続は、のちの相続手続きで説明・返還を求められる火種になります。
原則として、金融機関へ死亡の事実を連絡→凍結後に正規の払戻しや相続口座の手続きへ進みます。年金は支給停止・過払返還の規定があるため、年金窓口にも同時に連絡します。
禁止の例:キャッシュカード使用、家族カードの継続利用、名義変更前の解約金受領。迷う場合は必ず窓口に相談します。
届出準備の必携物(診断書・本人確認・印鑑)
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に提出します(戸籍法の要約、2024年)。提出前に、届出人の本人確認書類、故人の保険証・マイナンバーカード、印鑑(自治体により任意)、本籍確認用の住民票(本籍記載)や戸籍謄本をそろえます。
火葬許可の交付時刻と受け取り方法、斎場予約の流れも同時に確認します。
持ち物チェック:
- 死亡診断書(原本一体型の届書)。
- 届出人の本人確認書類。
- 本籍・筆頭者の確認資料(住民票/戸籍)。
- 印鑑(任意)と連絡担当者の連絡先。
\事前相談・無料資料請求/
死亡届提出までの流れと提出先
期限は国内7日・海外3か月、提出先は死亡地/本籍地/届出地のいずれかです。時間外は預かり扱いの自治体が多いため事前確認が有効です。
提出期限7日・海外3か月と時間外預かり
国内は「死亡を知った日から7日以内」、国外での死亡は「3か月以内」が目安です。休日や夜間は宿直窓口で預かり、正式処理は翌開庁日となる運用が一般的です。
遅延が見込まれる場合は、提出先に事情を連絡し、必要書類や受付可能時間を確認します。火葬許可の交付可否・時刻も併せて確認しておくと段取りが滞りません。
提出先の選び方(死亡地/本籍地/所在地)
提出先は「死亡地」「本籍地」「届出人の所在地」の市区町村役場から選べます(戸籍法の原則、2024年)。火葬許可の交付タイミングや斎場までの動線、移動負担の少なさで選ぶと実務的です。以下は比較の目安です。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡地 | 病院または自宅の所在地 | 受理〜許可交付が相談しやすい | 病院→役場→斎場の移動が短い |
| 本籍地 | 戸籍がある自治体 | 照会が最小限で済む | 遠方だと移動・郵送負担が増える |
| 届出地 | 届出人の住所地 | 他手続きと同時進行しやすい | 斎場予約が別自治体になる場合 |
火葬許可の取得手順と必要書類(数値は別章)
死亡届が受理されると火葬(埋葬)許可が交付されます。一般に手数料は数百円で、交付時刻は自治体の処理時間に依存します。
必要書類は、死亡診断書一体の届書、届出人の本人確認書類、場合により印鑑です。時間外提出は預かりのみで、許可の正式交付は開庁日になることがあるため、葬儀社と連携し交付時刻と斎場予約の順番を整えます。
手順の要点:
- 死亡診断書(届書一体)の記入と確認。
- 提出先役場で受理→火葬許可の交付。
- 交付後に斎場予約・搬送時間を確定。
- 許可証の原本管理と写しの配布先(葬儀社・火葬場)を決めます。
銀行対応の基本|出す前に決めるタイミングと手順
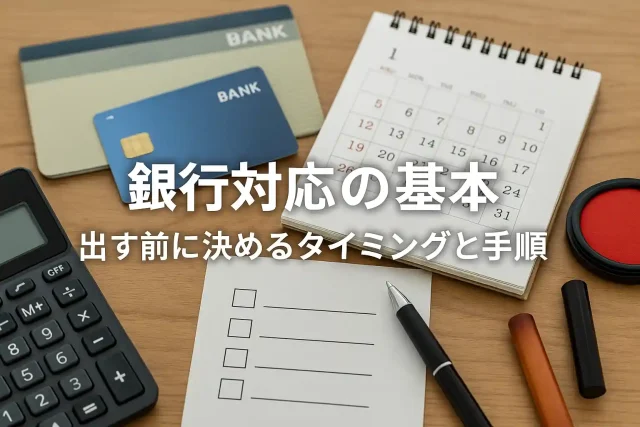
死亡の事実を把握したら早期に銀行へ連絡し、利用停止→必要書類の収集→正規の払戻しという順で進めます。
銀行への死亡連絡の時期と方法(支店/コール)
死亡届の提出準備と並行し、可能なら当日〜翌営業日に銀行へ連絡します。銀行は死亡の把握時点で口座を凍結します(金融機関の実務要約、2024年)。連絡方法は①取引支店へ電話→来店予約、②コールセンター→必要書類の案内、③ネット銀行は専用フォームの順が一般的です。
連絡時に用意する情報:氏名・生年月日・口座番号・取引支店・死亡日・連絡者と続柄。年金や公共料金の口座振替の停止も同時に確認します。のちの紛争防止のため、通話日時・担当者・指示内容をメモします。
口座凍結後の払戻しと葬祭費用の扱い
凍結後は「相続手続」で払戻します。多くの銀行は①相続人全員の同意書、②故人と相続人の戸籍類、③相続人の本人確認書類を要求します。
葬祭費用・当面費用に関しては、民法改正後の「預貯金の仮払い制度」を活用でき、1金融機関につき上限150万円かつ残高の1/3までが目安です(法改正実務の要約、2019施行・2024年時点)。申請者は相続人で、必要な領収書・見積・関係書類の提示を求められます。
実務ポイント:葬儀社への支払いは領収書の宛名と金額を明確にし、火葬許可・故人の戸籍除籍が揃い次第、相続書類の取得を急ぎます。
> 銀行手続きの比較表(実務の要点)
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡連絡 | 支店/コールセンター | 当日〜翌営業日 | 凍結後は入出金不可 |
| 仮払い | 相続人が請求 | 〜150万円/行・残高1/3 | 領収書・関係書類が必要 |
| 本手続 | 相続人全員の同意 | 2〜6週間 | 書類不備で長期化 |
してはいけない取引(死亡後の引き出し等・具体例)
死亡後のキャッシュカード利用、家族カードの継続使用、ネットバンキングの送金、定期預金の解約、名義変更前の解約金受領は避けます。
相続開始後の取引は、遺産の単独処分とみなされ、後日説明・返還や相続人間の紛争の原因になります。迷った場合は「一切触らず、銀行の指示に従う」を徹底します。
\事前相談・無料資料請求/
印鑑証明・戸籍類の整え方(相続の前提資料)
印鑑証明と戸籍一式は相続・払戻しの“土台”です。取得順と郵送・代理の可否を決め、早めに集めます。
印鑑登録と印鑑証明の取り方(本人/代理)
相続同意書や銀行手続きで相続人各人の印鑑証明が求められます。印鑑登録済みなら多くの自治体で即日交付、手数料は概ね1通300〜500円です。未登録者は登録が先で、本人確認書類と印鑑が必要です。代理取得は委任状で可能な自治体が多いものの、初回登録は本人限定の運用が一般的です。
実務の順序:①相続人の洗い出し→②各人の印鑑登録確認→③証明の同時取得→④原本は封筒で別保管。
戸籍・除籍・改製原の集め方(郵送/委任)
銀行の相続手続では、故人の出生から死亡までの戸籍一式と、相続人全員の現在戸籍が必要です。戸籍謄本は多くの自治体で1通450円前後です。
本籍地が遠い場合は郵送請求を使い、①請求書、②本人確認書類の写し、③定額小為替、④返信用封筒を同封します。代理人請求は委任状を添付します。複数自治体にまたがる場合は、取り寄せの順序を時系列(古い本籍→新しい本籍→除籍・改製原)で整理すると速く集まります。
本籍不明時の確認ルート(住民票・戸籍)
本籍が分からないときは、本籍記載の住民票で確認します。本人または同一世帯員が窓口・郵送で取得でき、手数料は200〜400円程度が相場です。
親族に確認する、過去の戸籍・不動産登記・保険・年金通知の控えを探すのも有効です。急ぐ場合、まず住民票で届書や銀行の初期確認を進め、その後戸籍一式で裏付ける二段構えが現実的です。
費用と期間の目安(自治体・金融機関の数字)
死亡届は無料。火葬許可は多くの自治体で日中交付、戸籍は450円/750円、印鑑証明は300円前後、銀行の払戻しは書類提出後2週間前後が目安です。
死亡届は無料/火葬許可の手数料と交付時刻の目安
死亡届の提出自体に手数料はかかりません。多くの自治体は夜間・休日も「預かり」は可能ですが、火葬許可証の(※使用禁止)交付は原則として開庁時間内です(例:横浜市は時間外は預かり、翌開庁日に審査・受理/2024年9月、公的情報。広島市は8:30〜17:15のみ交付、夜間交付なし/2025年3月、公的情報。刈谷市は金曜夜受付分は翌日9:30以降交付/2025年4月、公的情報)。
火葬許可の交付手数料は初回無料の自治体が多く、再交付は300円程度の設定が見られます。
- 可能なら日中に死亡届と火葬許可申請を同時提出します。
- 夜間・休日に提出した場合は、翌開庁日の交付時刻(例:9:30以降)を役所で確認します。
- 火葬予約は許可証の交付時刻に間に合う日程で押さえます。
<ケース>夜間に届出→翌朝交付となり、午前の火葬に間に合わず(※使用禁止)午後枠へ変更した事例があります。夜間提出時は翌朝の交付時刻を必ず確認します。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡届 | 役所へ提出(7日以内) | 無料 | 夜間・休日は預かり扱い(翌開庁日に審査) |
| 火葬許可交付 | 開庁時間に交付が原則 | 日中交付 | 夜間交付不可の自治体が多い/交付時刻要確認 |
| 火葬許可手数料 | 初回交付 | 無料 | 再交付は300円前後の自治体例あり |
印鑑証明・戸籍謄本の手数料と取得日数
戸籍は戸籍全部事項証明450円、除籍・改製原戸籍750円が標準です。印鑑登録・印鑑登録証明は自治体により1通300円前後が多く、本人が顔写真付身分証で申請すれば即日登録・即日交付できる運用例があります。代理申請や本人確認が郵送照会となる方式では数日要することがあります。
- 戸籍は必要範囲を整理(出生〜死亡まで・相続人分)。窓口でリスト化して依頼します。
- 広域交付を使うと本籍地以外でも現行戸籍が取れます(対象外の証明あり)。
- 印鑑証明は登録→証明書発行の順。即日狙いなら本人+写真付証明で窓口へ。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 戸籍全部事項証明 | 現行戸籍 | 450円/通 | 広域交付対象、混雑で後日渡しあり |
| 除籍・改製原戸籍 | 閉鎖・改製前の戸籍 | 750円/通 | 相続で必要になりやすい |
| 印鑑登録証明 | 印鑑登録後の証明 | 300円前後/通 | 本人即日可、照会方式は数日 |
口座凍結から払戻しまでの期間目安
銀行は死亡の連絡を受けると口座を凍結します。相続手続き一式(戸籍・遺言や遺産分割関連書類など)を提出後、払戻し完了は概ね約2週間が一つの目安です(大手行の案内/2025年時点)。
提出書類に不備がある、ローン・投信・貸金庫などがある場合はさらに長期化(数週間〜2か月)します。遺産分割前の仮払制度を使えば一定額まで先に引き出して葬儀費用等に充当できる場合があります。
注意点とトラブル回避(事実と感想を分ける)
届書記載の誤り・夜間提出後の交付遅延・銀行書類不備が遅延の三大要因です。事実と意見を分け、証跡を残して進めます。
差し戻しの典型ミス(氏名・筆頭者・本籍)
- 氏名の表記:戸籍と完全一致(旧字体・通称の混在禁止)。
- 筆頭者:現行戸籍の筆頭者を最新の戸籍で確認。
- 本籍:番地・枝番の抜けや旧本籍の記載に注意。
- 死亡診断書:押印・日付・死因の記載漏れの有無を確認。
- 提出前に第三者で相互確認。
- 夜間提出は翌開庁日審査・交付を前提に日程を組む。
銀行・カード会社で起こりがちな事例
- 口座凍結後の引落し停止:公共料金等は債務承継・名義変更の連絡を早めに。
- カード利用停止:死亡日以降の利用は無効・返金対応になり得るため、解約連絡。
- 書類不備:印鑑証明の有効期限や戸籍の取得範囲不足に注意。
- 払戻し時期:標準は(※使用禁止)書類提出後約2週間。混雑や追加審査で延伸。
記録・連絡経路・保管の実務要点
- 記録:提出日・窓口名・担当者・交付予定時刻をメモし、控えを保存。
- 連絡経路:役所・火葬場・葬儀社・銀行を単一ノートや共有アプリで連携。
- 保管:火葬許可・埋葬許可は納骨完了まで原本保管+コピー。
- 優先順:①火葬許可取得→②火葬予約→③戸籍・印鑑証明収集→④銀行手続。
よくある質問
医療機関・親族・葬儀社へ連絡し、死亡診断書を受領します。同時に本人確認書類や保険証、印鑑、戸籍関係の入手方法を確認します。
死亡届の提出準備と並行して早めに連絡します。連絡前後に口座から引き出すのは避け、凍結後は相続・葬祭費用の正規手続きで払戻します。
死亡後のATM引き出しやキャッシュレス利用、カードの継続使用、名義変更前の解約・解約金受取などは避けます。のちの紛争原因になります。
相続や払戻で相続人の印鑑証明が求められます。金融機関や手続き内容により必要人数・有効期限が異なるため事前確認が必須です。
本籍記載の住民票や本籍地の戸籍謄本で確認します。郵送請求や代理を使えば遠方でも手配できます。
国内は「死亡を知った日から7日以内」、海外は3か月以内が一般的です。連休や時間外は宿直窓口で預かり後、開庁日に処理されます。
金融機関が死亡を把握した時点で凍結されます。連絡が遅れると不審取引と誤解されるおそれがあるため、早めの連絡が安心です。
原則避けます。相続開始後の引き出しはトラブルの火種になり、後に説明や返還を求められる場合があります。
多くの自治体で印鑑登録済みなら即日交付可能です。未登録の場合は登録手続きが先で、代理や郵送の可否は自治体により異なります。
死亡届の受理後に交付されます。時間外預かりの場合は開庁日扱いとなり、交付時刻が翌営業日以降になることがあります。
カード会社へ利用停止を連絡し、未払を清算します。年金は支給停止・返還の規定があるため、年金窓口にも速やかに連絡します。
死亡届準備と並行して、住民票(本籍記載)→本籍地の戸籍→相続関係説明図の順で揃えるとスムーズです。
まとめ
日中の同時申請で交付遅延を防ぎ、戸籍450/750円・印鑑証明300円前後を目安に必要枚数を早めに収集し、銀行は書類提出後2週間前後で払戻し完了を想定します。
- 費用:戸籍450円/750円、印鑑証明300円前後、火葬許可初回無料(再交付300円程度の例)。
- 時間:火葬許可は夜間交付不可が多数で翌開庁日交付。銀行は提出後約2週間が一つの目安。
- 実務:日中提出・事前チェック・記録徹底。自治体・銀行の最新ページで金額・時刻・必要書類を確認。
\事前相談・無料資料請求/
