死亡届は葬儀屋に任せる?費用・提出先・手順と受け渡しの注意点

初めての手続きは迷いが多いものです。本記事は、提出先と期限、葬儀屋が代行できる範囲と費用、原本照合と写しの運用、火葬許可の受け渡しまで、失敗しやすいポイントを実務目線で整理します。具体例も交えて、今日から動ける段取りをわかりやすく解説します。

葬儀社ができること・できないこと
葬儀社は死亡届の提出・受領を代行できますが、届書の記入責任と署名は届出人本人です。提出先は死亡地・住所地・本籍地で、期限は7日以内です。
提出代行は可能/代筆は不可・署名は届出人本人
葬儀社は役所への持参・受け取り・連絡調整を担えますが、届書の主体はあくまで届出人です。署名は自署が原則で、第三者の代筆は認められません。
視力や手指の事情がある場合は、窓口担当者の指示に従い補助を受けます。実務では、喪主または親族が自宅・式場で記入し、葬儀社が役所へ持参する流れが最もスムーズです。
提出先と期限の要点:死亡地・住所地・本籍地/7日以内
提出先は「死亡地」「住所地」「本籍地」のいずれかの市区町村役場です。期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」が原則で、夜間・休日は時間外窓口で仮受理となる自治体があります。その場合、火葬許可証の交付は翌開庁日となる可能性があるため、通夜・告別式との前後関係を必ず確認します。
交付後は火葬許可証で日程が確定
死亡届の受理後に火葬(埋葬)許可証が交付され、火葬予約や式場の最終確定に進みます。火葬は「死後24時間以降」が原則で、交付のタイミングと火葬場の空き枠を合わせることが重要です(墓地・埋葬に関する法令 2024年時点)。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 時間外受付 | 警備室・当直で仮受理 | 夜間・休日も可 | 許可証は翌開庁日交付のことあり |
| 交付速度 | 受理→許可証 | 即日〜翌開庁日 | 連休・繁忙期は遅延しやすい |
| 持ち物 | 診断書原本・届書・身分証 | 必携 | 印鑑は不要の自治体も、念のため携行 |
具体例:連休前に時間外で仮受理を受け、許可証は休日明けに交付されました。火葬は翌々日午前に変更し、安置延長費用が増えない範囲で再調整できました。事前に「交付見込み時刻→火葬枠→搬送時刻」の順で確認したことが奏功しました。
\事前相談・無料資料請求/
葬儀社の死亡届サポートの実務
届書は家族が正確に記入し、葬儀社が提出・受領・連絡を担う分業が最短ルートです。時間外・連休は交付日が後ろ倒しになる前提でタイムラインを共有します。
当日フロー:診断書受領→届書記入→提出→許可証受領
- 医師から死亡診断書(または死体検案書)原本を受領。
- 届出人(多くは喪主)が届書に黒インクで記入・自署。誤記は窓口指示で訂正。
- 葬儀社が役所へ提出し、受理後に火葬許可証を受領。
- 許可証を式場へ持ち帰り、火葬場の予約枠と日時を最終確定。
・金融機関・年金・保険の手続きに備え、戸籍・住民票・法定相続情報一覧図の準備計画を同時に立てると再来庁を防げます。
時間外・連休の動き方と連絡体制
夜間・休日は仮受理で、許可証は翌開庁日交付が一般的です。連休や月曜朝は窓口が混みやすいため、安置延長や搬送時刻の変更余地をあらかじめ家族と共有します。
- 家族:届書の記入責任者、連絡先の一次窓口
- 葬儀社:役所・火葬場との連絡調整、許可証の受領・保管
- 寺院・式場:火葬時刻の確定後に読経・開場時刻を調整
グループチャットや共有メモで「交付予定」「予約番号」「受け渡し方法」を1枚に集約すると伝達ミスを防げます。
書類授受と権限の線引き(提出・受領/署名は本人)
届書の記入・署名は届出人本人が行います。葬儀社は提出・受領・交付物の運搬までで、内容責任者にはなりません。
| 項目 | 家族(届出人) | 葬儀社 | 役所 |
|---|---|---|---|
| 届書記入・署名 | 実施 | 不可(代筆不可) | 確認・指示 |
| 提出・受領 | 可能 | 代行可 | 受理・交付 |
| 許可証保管・引渡 | 受領後に保管 | 受領・搬送・引渡 | 再発行・証明発行 |
| 訂正対応 | 指示に従い実施 | 連絡・調整 | 訂正指示・処理 |
具体例:喪主が遠方のため、前日夜に届書を自署で完成。翌朝、葬儀社が提出し、昼前に許可証を受領。即日午後の火葬枠に間に合い、読経・搬送の遅延を回避できました。家族・葬儀社・役所の連絡窓口を一本化したことが時短につながりました。
代行費用と期間の目安(内訳・加算要因・タイムライン)
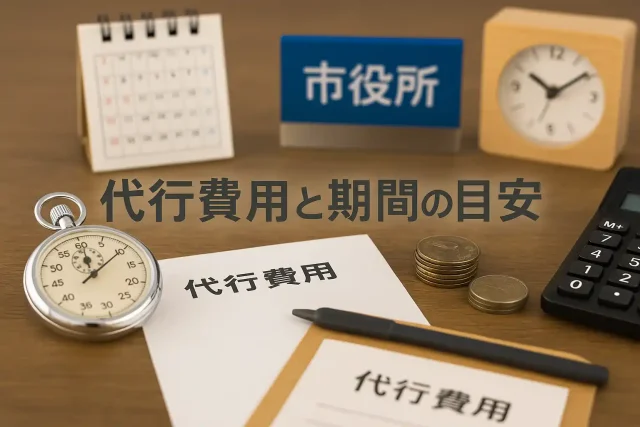
死亡届の提出は役所手数料0円ですが、葬儀社の代行は有料が一般的です。基本は数千円〜1万円台で、夜間・遠方・追加取得で増減します。
基本手数料の内訳(提出・受領・往復)
葬儀社の代行費用は「役所への持参・受領・返送(往復移動)・進捗連絡」の事務工数に対する対価です。地域相場は5,000〜15,000円(税込)が多く、式場常駐スタッフが提出する簡易ルートでは下限寄り、提出先が別市区町村で車移動が必要な場合は上限寄りになります。
死亡届そのものの行政手数料は不要で、受理後に交付される火葬許可証も発行料が無料または数百円の自治体が多数です。
費用の見え方(例)
・基本手数料:提出・受領・連絡一式
・移動費:実費または距離別加算
・書類準備サポート:記載確認・不備対応
加算要因:夜間・遠方・戸籍取得・郵送費
夜間・休日の提出は「時間外窓口で仮受理→翌開庁日交付」が多く、再訪が発生する分の人件費が加算されがちです。提出先が遠方の場合は距離・時間に応じて移動加算が生じます。
死亡届と同時に戸籍・住民票等の取得を依頼する場合は、実費に加え代行手数料が上乗せされます。戸籍手数料は目安として、戸籍全部(個人)事項証明450円、除籍・改製原戸籍750円。郵送請求を伴う場合は郵便実費(返信用封筒・書留等)も必要です。
加算が起きやすい条件
・夜間・連休前後で交付日が後ろ倒しになる
・提出先が別市区町村で往復1時間超
・戸籍束の通数が多い/郵送請求を併用
所要期間:即日〜翌開庁日/混雑時の遅延
基本的には、平日日中の受理で当日交付、時間外は翌開庁日交付が目安です。大型連休や年度替わりは窓口混雑で待ち時間が増え、交付が午後〜翌日にずれ込むことがあります。火葬は「死後24時間以降」の制約があるため、交付時刻と火葬場の空き枠を先に押さえると全体が短縮します。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 受理〜交付 | 届出受理→許可証交付 | 平日即日/時間外は翌開庁日 | 連休・繁忙期は遅延しやすい |
| 代行所要 | 葬儀社の持参・受領・返送 | 0.5〜1日 | 再訪発生時は+半日 |
| 追加取得 | 戸籍・住民票の取り寄せ | 即日〜数日 | 郵送請求は郵便日数分を加算 |
具体例:連休前の夜間に仮受理→休日明けの午前に交付。葬儀社は2回訪庁となり、基本手数料+夜間・再訪分の加算で総額約1.5万円(税込)。火葬は翌々日午前に確定し、安置延長費用の増加は最小化できました。
コピー運用と原本照合の実務
原本は窓口で照合し、以後は「原本照合済み写し」で回すのが効率的です。戸籍束は2〜3セットと法定相続情報一覧図で不足を防ぎます。
原本照合の可否確認と「原本照合済み写し」の作り方
まず、提出先に「原本照合後の写し受理」可否を確認します。可であれば、窓口で原本と写しを並べて照合し、受付印・担当印・照合表示(例:原本照合済)をもらいます。金融機関や保険会社はこの写しで受理することが多い一方、機関ごとに運用が違うため、葬儀社経由で事前確認すると二度手間を避けられます。
- 原本と同判のコピーを複数部作成する。
- 窓口で原本照合のうえ、各部に受付印等を付してもらう。
- 提出先の控え・自宅保管用・次機関提出用に仕分ける。
戸籍束・診断書の部数設計(銀行・保険・年金を想定)
被相続人の「出生〜死亡までの連続した戸籍一式」は同時提出が重なるため、2〜3セットの先行取得を目安にします。
死亡診断書は原本1通を携行し、原本照合済み写しを3〜5部程度確保すると、銀行・保険・年金・証券・公共料金へ並行提出しやすくなります。さらに、法務局の「法定相続情報一覧図(写し交付)」を作成すれば、戸籍束の持ち回りを減らせます(法務省運用の要約・2024年時点、作成は無料)。
目安(家計の取引先が多い場合)
・戸籍束:2〜3セット
・死亡診断書の写し:3〜5部
・相続人の印鑑証明:必要人数分(発行後の有効期限に注意)
保管・返却のルールと提出控えの残し方
原本・写し・控えを必ず分冊し、混在を防ぎます。提出した部数・窓口・担当者名・受付番号をメモし、返却予定がある原本には付箋で明示します。
返却待ちの原本があると他機関の手続きが止まるため、提出前に「返却有無」「返却時期」「郵送返却の可否」を確認します。紛失リスクに備えて、写しは日付入りでスキャン保管し、家族・葬儀社・代表相続人で共有します。
- 原本照合の可否と方法を各機関で確認
- 次の提出先分まで戸籍束・写しの残数を確保
- 受付印の位置・氏名表記のゆれを点検
- 返却予定の原本にマーキングし受け渡し方法を確定
具体例:銀行2行・保険2社・年金で同時進行。戸籍束3セットと死亡診断書写し5部を用意し、最初の銀行で原本照合済み写しを作って他機関へ横展開。返却待ちが発生せず、1週間で主要な解約・請求が完了しました。
\事前相談・無料資料請求/
トラブル予防(本籍誤記・重複提出・差し戻し)
誤記・重複提出・受け渡し不備は再訪の原因です。提出前に照合→確認→記録の順で点検し、遅延と余計な費用を防ぎます。
本籍・氏名・住所の照合と訂正手順
本籍・氏名・住所は、戸籍(全部事項証明や除籍等)と身分証・住民票の表記を必ず一致させます。旧字体や旧姓、枝番・部屋番号の有無は差し戻しの定番です。届書は黒インクで楷書記入し、修正液は使いません。誤記に気づいたら窓口の指示で訂正欄または二重線+訂正印で修正します(自治体記入要領の一般運用・2024〜2025年)。
照合の手順(提出前5分で点検)
- 戸籍→届書→身分証→住民票の順に表記を突き合わせます。
- 本籍の地番・字名、氏名の旧字、住所の枝番を再確認します。
- 医師作成の死亡診断書側の誤記は医師に訂正依頼します。
具体例:本籍の枝番を失念して提出直前に発見。届書に訂正欄を設け、窓口確認で受理され、手戻りを回避できました(戸籍・自治体運用 2024年)。
重複提出と原本回収遅延の回避(窓口確認事項)
「家族と葬儀社の双方が同一届書を提出」「原本を預けたまま他機関の手続きが止まる」などのトラブルを避けます。提出前に、誰が・いつ・どの窓口へ出すかを1枚のメモで共有します。原本は返却有無・返却時期・郵送返却可否を必ず確認します。
窓口で聞くこと(その場でメモ)
- 原本照合後、写し受理は可能か。
- 受理から火葬許可証交付までの目安(平日・時間外)。
- 返却の有無・方法(即時/後日郵送/窓口受取)。
- 受付番号・担当者名。
提出直前のチェックリスト
- 提出者(家族/葬儀社)を一本化
- 同一書類の二重提出を回避
- 原本の返却見込みと受け渡し方法を確定
- 受付印の位置・日付・氏名表記を確認
具体例:家族が直接提出予定だったが、葬儀社も移動中と判明。連絡調整で家族側の提出を停止し、重複提出を回避しました。
火葬場予約と許可証受領のスケジュール合わせ(遅延時の代替案)
火葬は「死後24時間以降」が原則で、許可証交付が遅れると予約時刻を動かす必要があります。時間外は仮受理→翌開庁日交付が多いため、許可証の受領時刻と炉の空き枠を先にスケジュール合わせします。
段取りのコツ
- 許可証交付見込み→火葬枠→搬送時刻の順で時程を確定します。
- 連休・週明けは遅延を見込み、安置延長費用や会場時間外料金の有無を確認します。
- 遅延時は「午後枠へのスライド」「翌朝一番枠」など代替スケジュールを事前に確保します。
具体例:時間外仮受理で交付が翌朝にずれ込む想定。火葬場に午後枠の仮押さえを依頼し、交付後すぐ本予約へ切り替え、式場と僧侶の時間も同報で修正して滞りなく進めました。
利用者の声と評価の傾向(事実と感想を分けて整理)
満足度は「迅速さ・説明力・見積明瞭さ」で決まります。評価は事実(所要・交付)と感想(対応印象)を分けて検討します。
高評価:迅速対応・役所ルートの最適化
高評価の共通点は、役所の混雑時間を避ける持参、時間外仮受理の翌朝一番受領、火葬場・寺院・式場との同時連絡です。届書の記載前に戸籍・身分証の表記を合わせる「事前点検シート」を使い、誤記・差し戻しを未然に防いだ事例も多いです。
- 交付見込み時刻の具体提示(「11:30±30分」など)
- 受付番号・担当者名の共有
- 許可証の受け渡し方法と時刻を先に確定
不満点:費用明細の不透明さ・交付遅延時の説明
不満は「代行費用の内訳不明」「再訪による追加費の事前説明不足」「交付遅延の連絡遅れ」に集中します。費用は基本手数料+移動+時間外+書類取得の区別を明示し、税込・非課税項目(戸籍等の手数料)を区分して示すと納得感が上がります。遅延時は、家族が判断できるよう代替案と費用影響を同時に提示します。
具体例:再訪が必要になったが、家族への連絡が遅れ不満に。以後は発生見込み段階で見積修正案を共有し、合意形成を先に行う運用へ改善しました。
改善策:書面見積・手続きの流れの共有・連絡記録
改善はシンプルです。①書面見積で「基本・移動・時間外・取得代行・実費(非課税)」を明示、②手続きの流れ(提出→受理→交付→火葬)を1枚図で共有、③連絡は時刻入りで記録します。
- 見積:項目/単価(税込)/数量/小計/実費(非課税)
- 手続きの流れ:受理時刻・交付見込み・火葬枠・引渡時刻
- 連絡記録:日時・連絡先・内容・次アクション
具体例:テンプレ導入後、問い合わせ往復が半減。家族は「何をいつ誰がするか」が一目で分かり、追加費の発生時も事前合意でトラブルがなくなりました。
チェックリスト|依頼前に確認すべき5項目
手戻りを防ぐ鍵は“誰が・どこへ・いつ・いくらで・何部”を先に固めることです。依頼前に以下5点を1枚にまとめます。
署名者・提出先・交付予定・費用内訳・コピー部数
最初に署名者(届出人)を明確にし、代筆不可を家族で共有します。提出先は死亡地・住所地・本籍地のいずれかを選び、交付予定(平日即日/時間外は翌開庁日が目安:自治体案内・2024〜2025年)を確認します。
代行費用は基本手数料+移動+時間外+書類取得の実費(戸籍等は非課税:自治体手数料・2024〜2025年)を見積書で分解し、コピー部数は戸籍2〜3セット・死亡診断書写し3〜5部を基準に調整します。
| 項目 | 内容 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 署名者 | 届出人本人の自署 | 1名 | 代筆不可 |
| 提出先 | 死亡地/住所地/本籍地 | いずれか | 最寄りで可 |
| 交付予定 | 受理→許可証 | 平日即日/時間外翌開庁日 | 連休は遅延 |
| 費用 | 代行+移動+時間外+実費 | 数千〜1万円台 | 内訳明示 |
| コピー | 戸籍/診断書写し | 2〜3/3〜5部 | 原本照合済み写し活用 |
許可証と原本の受け渡し方法/緊急連絡先
火葬場の枠確保に直結するため、許可証の受け渡し方法(式場・自宅・会場受付)と時刻を先に決めます。原本は返却有無・返却時期・郵送可否を窓口で確認し、原本/写し/提出控えを分冊します。緊急連絡先は家族代表・葬儀社担当・火葬場・寺院の4点を時刻帯付きで共有します。
提出直前チェック
- 署名者・提出者(家族/葬儀社)を一本化
- 交付見込み時刻と火葬枠の“時程合わせ”を決定
- 原本照合の方法と返却方法を確認
- 見積書に税込/非課税の別を明記
- 控えに受付印・担当者名・受付番号を記録
よくある質問
役所への提出・受領は代行可能です。ただし届書の記入責任と署名は届出人本人で、葬儀社は代筆できません。
原則7日以内です。火葬許可証の交付まで逆算し、時間外受付の有無と火葬場の空きを同時に確認すると最短化できます。
事務手数料として数千円〜数万円が一般的です。夜間・遠方・書類追加取得で加算される場合があるため、内訳を明示した書面見積が安心です。
銀行・保険・年金など同時進行なら、戸籍類は2〜3セット、死亡診断書の写しは複数部を目安に。原本照合の可否は機関で異なります。
窓口指示で訂正できます。修正液は不可で、訂正欄や二重線+訂正印等の所定方法をとります。診断書側の誤記は医師訂正が原則です。
書類の収集支援・提出代行・役所連絡は任せられますが、届書の署名・記載責任は届出人です。
届書の自署が原則で、第三者の代筆は不可です。視力・手指の問題がある場合は窓口の指示で補助を受けます。
受理後に交付されます。時間外提出だと翌開庁日になることがあり、日程調整に影響します。
提出・受領・役所往復が基本です。追加で戸籍取得や郵送費、夜間対応が加算されることがあります。
死亡地・住所地・本籍地のいずれかで受理されます。近くの役所で問題ありません。
原本照合済み写しで足りる機関もありますが、運用は機関ごとに異なります。事前確認が確実です。
まとめ
最短で進めるには、署名者・提出先・交付予定・費用・部数を事前合意し、許可証の受け渡しと緊急連絡網を固定します。
これだけで差し戻しや再訪、原本回収待ちによる遅延を大幅に減らせます。相場・交付所要は自治体・時期で変動するため、最終確認は電話一本で行い、当日の“時程合わせ”を葬儀社と共有します。
\事前相談・無料資料請求/
