葬儀の花マナー完全ガイド|供花の種類・相場・名前の書き方

「葬儀の花はどこに頼めばいい?」「供花の費用はいくらぐらい?」「連名で名前を書くときのルールは?」――葬儀の花には多くの疑問がつきものです。
大切な場面だからこそ、マナーを誤ると失礼になるのではと不安を抱く方も少なくありません。本記事では、初めての方でも安心できるよう、葬儀の花に関する基本知識を整理しました。
葬儀での花の基本マナーと依頼先の選び方
葬儀で供えられる花は、故人を偲び、参列者の気持ちを伝える大切な役割を果たします。しかし、初めて葬儀に参列したり準備を任されたりする場合、「どんな花を選べばよいのか」「どこに頼めばよいのか」と迷う人は少なくありません。
ここでは葬儀における花の基本マナーと、依頼先の選び方を整理して解説します。
葬儀の花の役割と意味
葬儀での花は、単なる飾りではなく故人への弔意や遺族への慰めの気持ちを表現するものです。一般的に「供花(きょうか)」と呼ばれ、会場に並べられるスタンド花やアレンジメントは、厳粛な雰囲気を保ちながら場を和らげる効果もあります。
また、宗教によって花の扱い方や意味が異なる点も理解しておく必要があります。例えば、仏式では白や淡い色合いの菊や百合が多く用いられますが、キリスト教では白い百合やカーネーションがよく選ばれます。
神道の場合は榊(さかき)と共に白を基調とした花が好まれるなど、宗派に応じた花選びが大切です。
実際に、菊を中心にした花が多い地域もあれば、洋花を取り入れた華やかなアレンジが一般的な地域もあります。このように、葬儀の花は「地域性」と「宗教性」の両方を意識して準備する必要があります。
葬儀の花はどこに頼む?主な依頼先と選び方
供花を手配する際の依頼先は、大きく分けて次の3つです。
- 葬儀社:葬儀全体を取り仕切るため、供花も一括して注文できます。式場に合わせた配置や数の調整がスムーズに行えるのが利点です。
- 地元の花屋:地域の慣習に詳しく、きめ細やかな対応が期待できます。個別に相談したい場合に便利です。
- オンライン注文:遠方からでも簡単に依頼でき、価格が明確な点がメリットです。全国配送に対応しているサービスも増えています。
例えば、故人が会社関係で多くの方に知られていた場合、スタンド花の数が多く並ぶことが想定されます。このようなケースでは葬儀社を通して一括管理したほうが全体の統一感が出やすく、遺族の負担も減ります。
一方で、個人での供花や親しい関係で贈る場合は、花屋に直接依頼して希望のアレンジを伝えるとよいでしょう。
葬儀社・花屋・オンライン注文の違い
依頼先ごとの特徴を比較すると、以下のような違いがあります。
- 葬儀社:手間がかからず安心だが、料金はやや高めになる傾向。
- 花屋:自由度が高く要望を反映しやすいが、式場との調整は依頼者が確認する必要がある。
- オンライン注文:利便性と価格の明確さが魅力だが、実際の仕上がりを事前に確認できない場合がある。
初めて葬儀の花を手配する人には、式場や葬儀の規模に合わせて柔軟に対応できる葬儀社を通した依頼が無難です。その上で、個別に気持ちを伝えたいときには花屋やオンラインサービスを併用すると良いでしょう。
スタンド花・供花の種類と相場
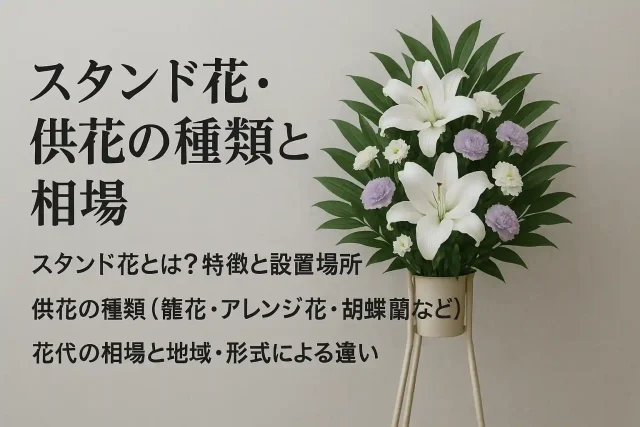
葬儀で供えられる花にはいくつかの形式があり、その中でも特によく見られるのが「スタンド花」と「供花(きょうか)」です。
どちらも故人を偲び、参列できない場合でも気持ちを伝える方法として広く利用されています。ここでは代表的な種類と特徴、さらに気になる相場について解説します。
スタンド花とは?特徴と設置場所
スタンド花とは、鉄やアルミのスタンドに大きな花をアレンジして飾るもので、葬儀会場の入口や祭壇の両脇に設置されるのが一般的です。高さがあり、遠くからでも目立つため、弔意を表すと同時に会場全体を華やかに整える役割を果たします。
スタンド花には1段と2段があり、2段タイプはより豪華に見えるため、取引先や団体から贈られるケースが多いです。個人で贈る場合は1段スタンドが選ばれることが多く、費用とのバランスを考えて選択されます。
実例として、会社関係者が複数のスタンド花を贈ると、会場の入口にずらりと並び、弔問客にも「多くの人に慕われた人物」であることを伝える効果があります。
供花の種類(籠花・アレンジ花・胡蝶蘭など)
供花にはスタンド花以外にもさまざまな形式があります。代表的なものを以下にまとめます。
- 籠花(かごばな):白や淡い色合いの花を籠にアレンジしたもので、祭壇前や棺の近くに置かれることが多い。落ち着いた印象を与える。
- アレンジ花:洋花を使った華やかなスタイル。親しい友人や家族から贈られるケースに多い。小ぶりで持ち帰りもしやすい。
- 胡蝶蘭:格式高い花として知られ、特に社葬やお別れ会で選ばれる。長持ちするため葬儀後も自宅や会社に飾れる点が特徴。
供花の種類は地域や宗派によって異なり、例えば関西地方では籠花が主流、首都圏では洋花を取り入れたアレンジが増えています。地域性に配慮した選び方が重要です。
花代の相場と地域・形式による違い
供花やスタンド花の価格は、花の種類や大きさによって大きく変わります。目安は以下の通りです。
- スタンド花(1段):1.5万円〜2万円前後
- スタンド花(2段):2万円〜3万円前後
- 籠花・アレンジ花:1万円〜2万円程度
- 胡蝶蘭:2万円〜5万円以上
会社や団体から贈る場合は2万円〜3万円台が主流で、個人の場合は1万円〜2万円台が多い傾向にあります。また、都市部では全体的に高め、地方では比較的リーズナブルな料金設定になることもあります。
例えば、首都圏で2段スタンド花を依頼すると税込み3万円前後になることが多いですが、地方都市では2万円台で注文できることもあります。遺族の意向に合わせつつ、地域相場を確認しておくと安心です。
さらに、葬儀社を通じて注文すると手数料が上乗せされる場合があるため、費用を抑えたい人は花屋やオンラインショップで直接依頼するケースも増えています。
いずれにしても大切なのは「金額よりも心を込めること」です。無理のない範囲で、故人や遺族に失礼のない形で準備することが何よりのマナーといえるでしょう。
供花の名前・連名の書き方と注意点
供花を贈る際に欠かせないのが「名札(立札)」の記載です。名札には誰から贈られた花かを示す役割があり、遺族が感謝の気持ちを伝えるための重要な手がかりとなります。
しかし、名前の書き方や連名のルールには細かなマナーがあり、間違えると失礼にあたる場合もあります。ここでは個人・家族・会社といった立場別に注意点を解説します。
個人で供花を贈る場合の名前の表記
個人で供花を贈る場合は、フルネームを縦書きで記載するのが基本です。姓のみや名前のみでは誰から贈られたものか特定しにくいため、必ず氏名を明記します。一般的には「○○ 太郎」と記すか、「○○家」など家名で表すこともあります。
例えば、友人として贈る場合は「山田 太郎」、親族として家を代表して贈る場合は「山田家」と表記するのが適切です。また、肩書きや役職は通常不要ですが、故人や遺族との関係性を明確にしたい場合には付け加えることもあります。
家族や親族で連名にする場合のマナー
家族や親族が連名で供花を贈る場合、書き方には次のようなパターンがあります。
- 夫婦で贈る場合:「山田 太郎・花子」
- 親子で贈る場合:「山田 太郎・一郎」
- 兄弟姉妹など複数人の場合:「山田 三兄弟」や「山田家一同」
人数が多い場合には一人ひとりの名前を書くとスペースが足りなくなるため、「○○家一同」とまとめる方が望ましいです。特に親族一同で贈る場合は「○○家親族一同」と表記するケースもあります。
注意したいのは、連名であっても故人や遺族に分かりやすい形にすることです。遺族が礼状やお返しを準備する際の参考になるため、省略しすぎないように配慮が必要です。
会社・団体から贈る場合の表記ルール
会社や団体から供花を贈る場合は、会社名・部署名を明記するのが一般的です。例えば「株式会社〇〇 営業部一同」「有限会社△△」といった形です。役職名を含めることもありますが、通常は組織名を優先します。
特に取引先や顧客関係の場合は、正式名称を省略せずに記すことがマナーです。「(株)」や略称は避け、「株式会社」と正しく表記しましょう。また、複数の社員が連名で贈る場合は「〇〇株式会社 営業部一同」とまとめるのが一般的です。
実例として、取引先の葬儀に「株式会社○○ 代表取締役社長 山田 太郎」「営業部一同」と2つのスタンド花を並べるケースもあります。これは会社を代表して贈る花と、部署単位で贈る花を分けることで、より丁寧な弔意を示す方法です。
いずれの立場であっても、名札の記載は遺族が誰からの供花かを把握するための大切な情報です。「誰から贈られた花なのかが一目で分かる表記」を心掛ければ、失礼のない供花手配につながります。
供花を手配するときの流れと注意点
初めて供花を贈る場合、「注文のタイミングは?」「どのように手配すれば良いのか?」と不安になる方も多いでしょう。供花は葬儀に参列できない場合でも故人や遺族に気持ちを伝える手段となるため、手配の流れや注意点を理解しておくことが大切です。ここでは実際の流れと、失敗しないためのポイントを整理します。
注文から設置までの一般的な流れ
供花を手配する場合、基本的な流れは次の通りです。
- ① 葬儀日程と会場を確認:まずは遺族や葬儀案内状で日程・会場を把握します。葬儀社を通じて確認できる場合もあります。
- ② 依頼先を選ぶ:葬儀社、花屋、オンライン注文のいずれかを選びます。式場との調整が必要な場合は葬儀社を通すのが安心です。
- ③ 名札の内容を決める:個人名、連名、会社名など、立場に応じて正しく表記します。
- ④ 注文を確定する:供花の種類や金額を指定し、支払い方法を決定します。
- ⑤ 会場に設置:通常は葬儀社や花屋が会場に直接届けて設置します。贈り主が持参する必要はありません。
この一連の流れを押さえておくと、短時間でもスムーズに供花を手配できます。
故人や宗派に合わせた花選びの工夫
供花を選ぶ際には、故人の好みや宗派に合わせることも大切です。例えば、生前に白い花が好きだった場合や、華やかな雰囲気を好んでいた場合には、遺族に相談してアレンジ花を選ぶのも一つの方法です。
また、宗教ごとに選ばれる花も異なります。仏式では菊や百合など白を基調とした花が一般的ですが、キリスト教では白い百合やカーネーション、神道では榊と合わせて白花が使われます。地域によっては洋花を多く取り入れることもあり、葬儀社に相談すると安心です。
「豪華にしたいが遺族に負担をかけたくない」といった場合には、相場を踏まえつつシンプルで上品な花を選ぶことが適切です。
香典や供物とのバランスを考える
供花を贈る際に気をつけたいのが、香典や供物とのバランスです。すでに香典を包む予定がある場合、高額な供花を贈ると遺族に気を遣わせてしまうことがあります。逆に、参列できず供花だけを贈る場合は、やや豪華な花を選ぶことで気持ちを伝えることができます。
例えば、親族として参列する場合は「香典+1万円程度の供花」、会社関係者として贈る場合は「供花2万円前後」が目安です。複数人で費用を出し合い、連名で供花を手配する方法もあります。この場合、一人あたりの負担は少なくても、立派な花を贈ることができます。
さらに注意したいのは、葬儀によっては「供花・供物は辞退」とされている場合があることです。その場合は無理に手配せず、遺族の意向に従うことが最も大切です。
供花の手配は単なる形式ではなく、故人を敬い、遺族に寄り添う気持ちを表す行為です。手配の流れと注意点を理解しておけば、慌てずに心を込めた供花を贈ることができるでしょう。
まとめ|葬儀の花は心を込めて準備しよう
葬儀に供える花は、故人を偲び遺族に寄り添う大切な意味を持ちます。スタンド花や籠花、アレンジ花など形式はさまざまですが、共通しているのは「心を込めて贈ること」です。豪華さよりも、故人や地域・宗派にふさわしい花を選ぶことがマナーといえるでしょう。
依頼先には葬儀社・花屋・オンライン注文があり、それぞれ利点があります。葬儀社は安心感があり、花屋は柔軟な対応が可能、オンライン注文は遠方からでも依頼できる便利さがあります。状況に応じて選びましょう。
また、名札の書き方も重要です。個人ならフルネーム、家族なら「〇〇家一同」、会社なら正式名称を省略せず明記するのが基本です。遺族が誰からの供花か分かるように心配りを忘れないことが大切です。
供花は形式的な慣習ではなく、感謝や尊敬の念を伝える手段です。迷ったときは葬儀社や花屋に相談し、遺族の意向を尊重しながら準備すれば安心です。心を込めて準備した花は、故人への最後の贈り物となります。